『流人道中記』著者・浅田次郎さんインタビュー
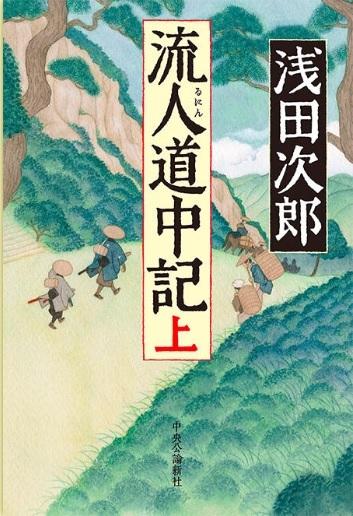
――本作は『読売新聞』朝刊で連載された道中物語でした。執筆中、主人公の二人と一緒に旅をしている気分はありましたか。
それはありました。透明人間になって二人の旅に同行しているかのような臨場感で、毎日楽しく小説を書きました。以前、街ですれ違った人に対して「どこかで見たことあるな」と思ったのですが、よく考えたら自分の小説の登場人物のイメージとそっくりだった、ということがあります。玄蕃と乙次郎とは、江戸から青森まで一緒に旅をしたことになるので、僕にとっては実在の人物に近いですね。
――以前、本誌で連載していただいた『一路』は中山道を舞台にした時代小説でした。今作の舞台は奥州街道。取材の際、違いは感じましたか。
まず中山道は宿場がそのまま残っている箇所が多かった。どうやら後に引かれた鉄道が街道に沿って造られたので、観光地として保存されたらしい。比べて、奥州街道は遺構があまり残っていませんでした。宮城県の有壁にある本陣など、きれいに残っている場所も一部はありますが、宿場町の縁を偲べなかった。ただ、空気感は十分に堪能できました。北に向かうことにより滲み出る寂寥感というものを、この作品には活かしたかったんです。 「北に向かう」という行為には、どこか深くに沈んでいくような、不思議な感覚があります。大阪に行くのと盛岡に行くのでは距離はほとんど変わらないのだけれど、なぜか北に行くほうが遠く感じませんか。これは日本だけでなく、『中原の虹』の取材で中国の東北部に取材に行った時も、まったく同じ印象を覚えました。『中原の虹』で北国の寂寥感を描いた経験も、この『流人道中記』に活かせたのではないかと思っています。
――浅田さんの「北」を描いた作品には『壬生義士伝』もあります。
「おもさげながんす」とか、南部の言葉が登場するので、近い印象を持った読者もいるかもしれませんね。これは主人公の二人が南部領に入った時に、物語がぐっと深く沈み込むようにしたかったので、登場人物の言葉を意識的に盛岡弁に切り替えました。遠くへ来た、というイメージを持たせ、その土地の人間性を想像させるのに、方言というものは強い力を発揮しますから。
――北へ向かう道中の風景描写も印象的でした。
小説に花鳥風月を描くことは、日本文学である限り必要だと思っています。美しさというものは、人間にしか理解できない概念ですから。「花より団子」という言葉があるけれど、人間であれば本当は飯より花を選ぶべきではないでしょうか。それに日本には、四季という背景が、日常の中に存在しています。四季の風景に物語を載せることこそが、日本文学の正しい在り方だと思います。
――この物語のテーマは「懐疑」だと聞きました。現代の日本において、この意識は薄くなっていると思いますか。
平和が長く続く時代や国が成長を続ける時代は、懐疑しない時代になるんです。僕が学生時代、周囲の人たちは学生運動の只中にあり、みんなが懐疑の意識を持っていた。その後、高度成長期を経て暮らしが豊かになっていくうちに、だんだん物事を疑わなくなっていったんです。バブルの時代なんて、長くは続かないと分かりきっていた。テレビや新聞で、バブル崩壊の危険性も指摘されていた。なのに、誰も後のことを考えようとしなかった。今の世の中も、まだその延長線上にあるように思えます。新型コロナウイルスの感染拡大に対する国の方針を見ても、当初は最悪のことを想定していなかった。希望的観測にもとづいた対応でした。 江戸時代は約二六〇年間、他国の侵略も内戦もない、世界に類を見ない平和な世でした。幕府が支配する軍事政権であったにもかかわらず、です。江戸の町はものすごく治安がよく、おそらく殺人事件の数も現代より少ない。戊辰戦争ですら史料を見ると、お互いに使者を立てて話し合いの場を設けている記述が多く目につく。どこまで本気で戦争をしていたのかすら、疑わしいんです。この長い平和の中で築かれた楽観主義が、日本人の国民性として根付いてしまったのではないでしょうか。
――楽観主義的な国民性を持つ日本が明治維新以降、急成長を遂げられたのはなぜでしょうか。
それはやはり教養主義の力が大きかったと思います。だけどその教養主義も近年、崩壊してきている。文学部不要論をはじめとして、哲学や文学までも不要なものだという考え方があります。でも、これこそ日本的な教養であり、すべての知識の土台となっているのではないか。今後、経済や科学技術の発展に重きを置き、義務教育もこれらを重視したものにシフトしていったとすると、教養主義の敗北ということになる。そうなれば、日本はあっという間に没落するのではないだろうかと危惧しています。今の時代も、それぞれの人が自分なりの思想、哲学を持つべきです。 「読書離れ」と言われて久しいけれど、それも小説というものが、必ずしも必要なものだとは考えられなくなったからではないでしょうか。でも、小説を読まない人は、想像力が培われない。想像力がない人は、会話をしていても、どこか面白くないんです。
――ネットの文章だけではなく、紙の本を読んでこそ培われるものはありますね。
インターネットの世界から「物知り」はたくさん生まれるかもしれないけれど、本当の「知識人」は生まれません。知りたいことの答えが、検索すればすぐに分かってしまう世界では、「考える」「想像する」という力は育ちませんから。この小説を書き始めるとき、「懐疑」というテーマを決めるとともに、主人公の二人には「求道者と悩める弟子」というイメージを持たせました。 新型コロナウイルス感染症の流行で今作のサイン会はすべて中止になってしまいました。これは残念なことだけれど、外に出られない時だからこそ、ぜひこの本を読んで主人公の二人とともに旅をしてほしい。たくさん本を読んで想像力を養い、懐疑する心を培ってほしいと思います。
(『中央公論』2020年5月号より)






