権力の腐敗と翻弄される私たちの姿~目からウロコの名作再読・『動物農場』(ジョージ・オーウェル著)
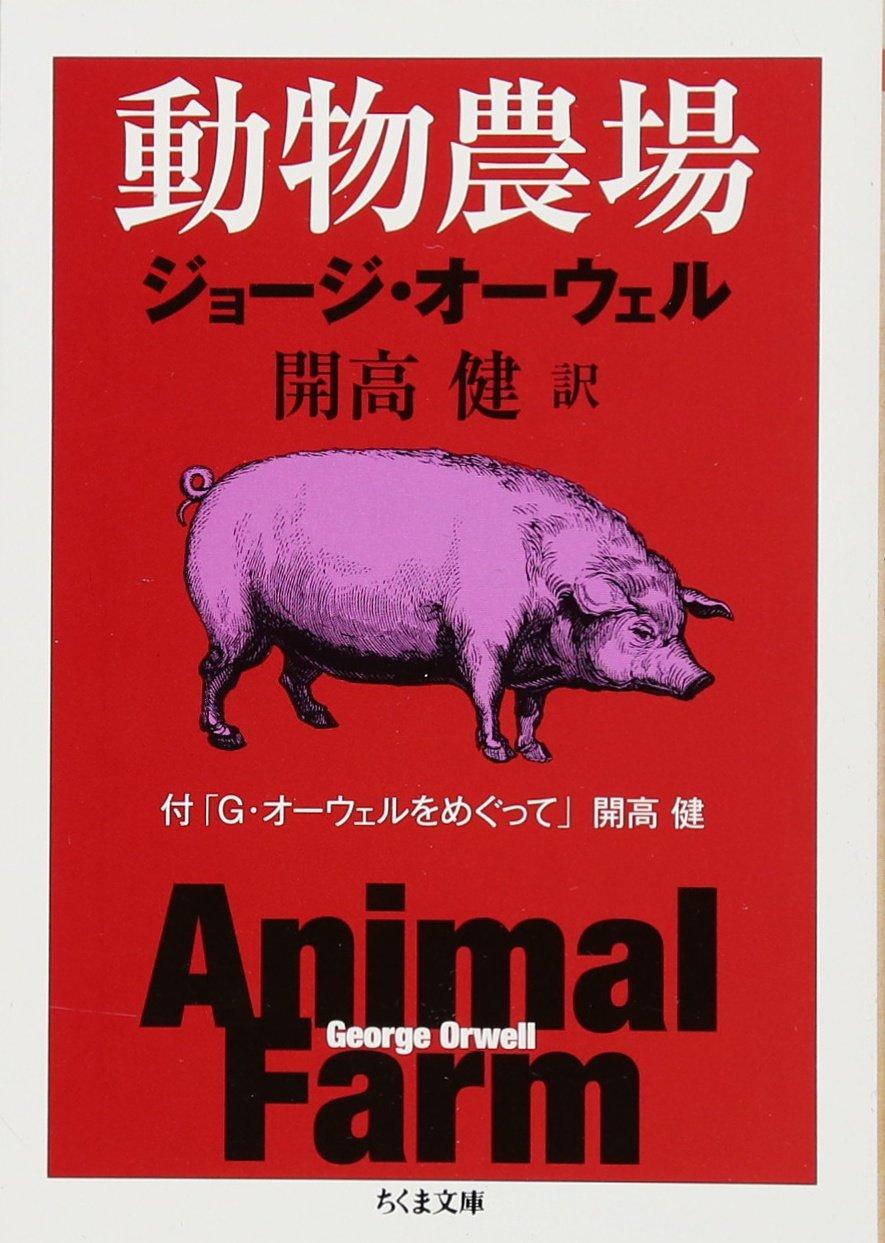
評者:植村秀樹(流通経済大学教授)
高校を卒業し、「一度くらい花のお江戸で暮らしてみよう」と田舎から出てきた私が、木枯らしが吹き始めた頃だったか、少しは受験勉強をせねばと書店で手に取ったのが『動物農場』の原書"Animal Farm"だった。オーウェルの名前ぐらいは知っていたし、薄いペーパーバックは、一見すると初学者でも読めそうに感じられた。辞書を片手に読み始めるやいなや、その面白さにたちまち引き込まれた。最後のページにたどり着いて、仰天した。無知で純朴な田舎青年には、そのラストシーンはあまりに衝撃的だった。
何とか大学に入り、マルクス主義を少々かじると同時にソ連型社会主義(スターリニズム)の実態も知ると、あれは寓話のかたちを借りたソ連批判の書だったのだとあらためて納得した。
とはいえ、執筆当時の英国とソ連は、ナチス打倒のために相携えて共に戦う間柄だった。「真実は、たとえ痛みを伴うとしても、癒すためにしか傷つけない」という名文句を序文に戴くアンドレ・ジッドの『ソヴィエト旅行記』がそうであったように、当時としては勇気のいる出版だったのではなかろうか。ところが、書店に並ぶやいなや、たちまちベストセラーになり、日本でもGHQからすぐに翻訳許可が下りた。反共・反ソ宣伝に好都合だからだ。
話の筋は単純といえば単純だ。ある日、とある農場で、動物が人間を追い出し、動物の、動物による、動物のための「動物農場」が誕生した。そこにはレーニンを思わせる者(豚)、スターリン、トロツキー、さらにはトハチェフスキー将軍らしき者(馬)まで登場する。動物の楽園になるはずが、一部の動物とその取り巻きが新たな支配者となり、やがて粛清の嵐が吹き荒れ、動物たちは過酷な暮らしを強いられる。革命は裏切られた。
大学を卒業すると間もなく、オーウェルのもう一つの名作『一九八四年』の年がやってきた。その数年後にはベルリンの壁が崩壊し、続いてソ連自体も解体した。動物農場は再び人間が支配する農場(資本主義)に戻ったというわけだ。その頃には「歴史の終焉」をうそぶく者まで現れ、この作品も歴史的役割を終えたかに思われた。
しかし、そうではない。共産主義国における権力の腐敗や権力者の裏切り、つまり革命の失敗を描いたものとかつての私は理解していたのだが、それにとどまるものではない。
詭弁、強弁、さらには恫喝。自分に不都合な報道を「フェイク」と罵ったり、公文書を改ざんしたり廃棄したり。「お友達」優先の権力私物化に「ご飯論法」まで、今、私たちの眼前で繰り広げられている政治が描かれている。言論は歪められ、格差は拡大し、あまつさえ戦争に駆り立てられる。
さらに重要なことは、今ここにある政治のありようを暴露するだけではなく、支配される者たちに警鐘を鳴らしていることだ。豚に翻弄される愚かな動物の姿はあまりに痛々しい。騙されるだけではなく、裏切ったり、日和見を決め込んだりと、動物たちの愚かさもまた、それぞれなのであって、まさに今の私たち自身の姿をそこに見る思いがする。寓話であることによって、その真実味は一層増している。
どんな政治学の教科書も文学と政治の融合に成功している『動物農場』にはかなわない。「象を撃つ」「絞首刑」などオーウェルの珠玉の作品は、通り一遍の観察からは生まれ得ない。英イートン校を経てインド帝国警察に勤務し、パリやロンドンでどん底暮らしまで経験したオーウェルならではの名作群の中にこれを置いてみれば、人と社会を見る眼が深くその実相をえぐり出していることが容易に感得されよう。
ソ連とその勢力圏の瓦解を含むこの四〇年を経て再読した私は、最後に、やはり天を仰いだ。
(『中央公論』2020年6月号より)
一九五八年愛知県生まれ。政治学者。研究テーマは戦後日本の外交・安全保障。著書に『「戦後」と安保の六十年』『自衛隊は誰のものか』『暮らして見た普天間』などがある。






