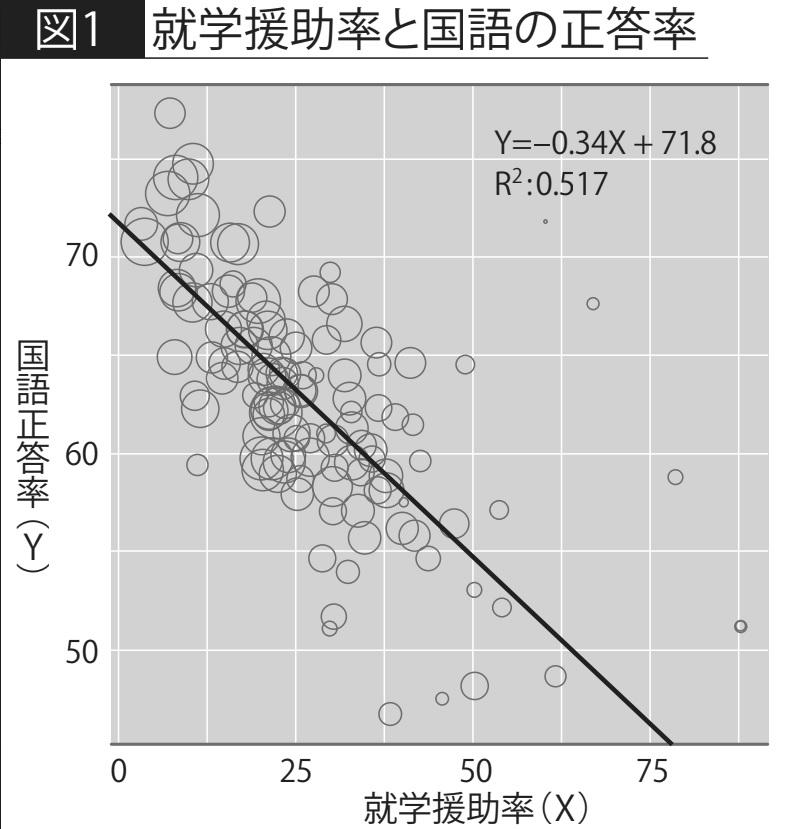「災害は忘れたころにやってくる!」
宮城県石巻市の市報「いしのまき」の三月号には、こう大書された災害対策の特集記事が掲載されている。発行日は今年三月一日。二〇一〇年二月末に南米チリ沖で発生した地震による津波の襲来から、ちょうど一年の時期にあたる。「津波から逃れるために」と題した項目では、「津波警報や避難指示を待たず、直ちに海から離れ、急いで高台や鉄筋コンクリートなど丈夫な建物の2階以上に避難しましょう」と明記してある。
この市報発行から一〇日後に発生した東日本大震災から三ヵ月以上が過ぎた。死者・行方不明者合わせて二万数千人を数える事態になってしまったいま、直前の・警告・はあまりにも空しく響く。石巻市内だけで六〇〇〇人近くが死亡・行方不明になったのだ。
中でも、全校児童一〇八人のうち六八人が一瞬にして命を落とし、六人が行方不明になった市立大川小学校の悲劇は、教育現場を襲った災害として歴史に深く刻みこまれることになった。だが、それだけに限らない。単なる天災で終わらせることができない背景があるからこそ、長く記憶に留められるかもしれないのだ。
私は約三ヵ月ぶりに石巻市を訪れ、大川小がある釜谷地区とその周辺を中心に取材して回った。つぶれた家屋や車がそこら中に散乱していた三月の宮城訪問時と比べると、瓦礫はかなり取り除かれている。だが、新築される家があるわけでもない。かつて家屋や漁業施設が寄り添うように建ち並んでいた一帯は、人気のない砂漠のような太古の姿をさらけ出し、鉄筋コンクリートの廃墟がいくつか無残に残されているだけだ。その一つが、子供の歓声が消え、無機質な静けさに包まれた大川小学校だった。すぐ後ろに見える針葉樹林に覆われた高さ数十メートルの小高い山の塊が、ひときわ存在感を示していた。
裏山に逃げていれば......
「いまは考える時間ができて、余計に悲しみと悔しさが増しています。なんでいつものように『ただいま』と元気に帰って来ないのか......」
紫桃さよみさん(四十五歳)は、五年生の次女千聖さん(十一歳)を失った。溢れる涙を抑えながら「悔しさ」を口にしたのは、市教委や学校側の対応に対する疑問を拭えないからである。 「私も、ほかの亡くなった子の親も、『どうして助けてあげられなかったのか』と自分を責める日々なんです。でも、子供たちは学校の管理下にあって、先生の判断を仰ぐしかなかったんです。なぜ裏山に逃がしてくれなかったのでしょうか......」
市教委の説明や地元住民の証言によると、あの日午後二時四十六分に地震が発生した際、子供たちの多くは「帰りの会」の最中で、机の下に隠れた。下校を始めていた一部の児童も学校に戻ってきた。放送機器は使えず、教務主任が校庭へ避難するよう指示しながら校内を回った。三時ごろになって児童が校庭に集合し、教員が点呼を取り始めた――。
ここまでは普通に考えられる対応だ。時間的にもたついた様子もない。大川小は津波の際の市の避難場所に指定されているし、校庭に出るのがまずは最善と思われた。だが、この直後、現場にいた一一人の教員たちは・迷走・を始める。このまま校庭に居続けるか、津波を想定して逃げるとすればどこに避難すれば良いのか、すぐに結論が出なかったのだ。校舎の西脇にある裏山に逃げるべきだとの声も出たが、「倒木や雪がある。余震も続いている」などと異論が出た。鉄筋コンクリート二階建てで高さが一〇メートルある大川小に屋上がなかったことも、選択肢を狭めた。
やがて、子供たちは泣き叫ぶなどして動揺し始めた。恐怖のあまり吐く子もいた。とにかく校庭を出発し、北上川に架かる新北上大橋脇の堤防道路の方向に一列になって避難し始めたのは、三時二十五分ごろになってからだ。校庭からは約七メートルの高さがある。
一部の親たちが続々と車で駆けつけて我が子を連れ出し、児童の数は約八〇人に減っていた。市の広報車が、津波の接近を伝えながら慌ただしく周辺を走る。と、次の瞬間、校舎西側にある北上川と東側にある海岸の二方向から、一〇メートルを超す山のような津波が、轟音を響かせながら迫ってきた。そして運命の三時三十七分、堤防道路付近にいた子供たちを一気に飲み込んだのだ。教員も九人が死亡し、一人の行方がいまも分からない。校長は不在で無事だった。
「一一日後、校舎から一キロほどの場所で遺体が見つかりました。水を飲んだ様子もなく、穏やかな表情でした。津波に遭う前日には『一二年間育ててくれてありがとう。迷惑かけてきたけど心の中では感謝していました』なんて、普段は口にしたこともない言葉を書いた手紙も寄こしてくれたのに......」
卒業を目前にした六年生の三男佐藤雄樹君(十二歳)を亡くした父親の和隆さん(四十四歳)は、沈痛な表情で言葉を絞り出す。微笑みを浮かべる遺影の傍らには、得意だった野球のバットとグローブが丁寧に添えられていた。
「地震発生のとき、仕事で市内の離れた所にいたんです。普通の揺れじゃなくて、地球が壊れるんじゃないかと思いました。すぐに自宅や学校がある地区に帰ろうとしましたが、一〇分で戻れるところが渋滞で一時間以上かかってしまった。時計を見て、『雄樹はまだ学校にいるな』と思いました。絶対に安全だと信じていたんです。あの状態では、裏山に逃げるしかないのに、どうして......」
あのとき、車のラジオからは「津波の高さは六、七メートル」と流れていた。絶対に津波は来ると思った。でも、あそこには裏山がある。子供が飛んで行った野球のボールを取りに行くことがよくある場所だ。下草もなく、登りやすい場所だった。「あそこに逃げれば大丈夫だ」と言い聞かせていたが、実際はまったく別の方向に向かってしまったのだ。
紫桃さんと同様、最愛の我が子を助けられなかった自責の念を抱きつつ、学校側の対応への不信感を隠さなかった
「なぜ大川小でだけ、こんなに多くの犠牲が出たのか。私は学校側の津波への備え、それに津波襲来時の対応が間違っていたと思います。津波が来るまでの五一分もの間、何をしていたのか......そう思わざるを得ないのです」
けれども、もっと理解できないのは「事後対応」だと訴えた。
「校長は遺族をすぐに訪問せず、捜索にも協力的ではありませんでした。私たち遺族が『いったい何が起きたんだ』と途方に暮れているときに、学校側はいつまでも説明しようとしなかった。災害から一ヵ月経ってようやく説明会を開いたんです。誠意が感じられなかった」
この四月九日の保護者説明会でさえ、重大な結果への謝罪はなく、避難の経緯や防災マニュアルの詳細についての説明にも、多くの遺族は納得しなかった。父母たちはさらなる説明を求めて「要望書」を市教委に提出し、六月四日午後七時に再び説明会が開かれたのだった。
二度目の説明会の会場は、北上川下流の北岸に広がる山側に位置する別の小学校だった。保護者約七〇人のほか、亀山紘市長、市教委幹部、校長が出席。学校側は、裏山に逃れて助かった男性教諭や無事だった児童への聞き取り調査の結果を基に、地震から津波到達までの経緯を説明した。
次に、学校に防災マニュアル自体は存在したものの、唯一、津波を避けられたと思われる裏山を想定した二次避難マニュアルを準備していなかったことを認め、それによって時間のロスが生まれたとの認識を示した。海岸から四キロ離れた大川小には、もともと大津波が来ると想定していなかったとも明かした。
実は、市教委は昨年二月六日付の文書で市立学校に対し、津波に対する二次避難場所を設定するよう指導していた。海岸沿いを中心にこうした対応をとっている学校もあり、多数の子供たちが助かっている。だが、大川小が作成したマニュアルには、津波襲来の危険性を軽視していたのか、「高台」というあいまいな記述しかなかった。市教委もそれについて点検や指導はしていなかったのだ。
説明会では、最後まで学校側からは、明確に責任を認めて謝罪する言葉は聞かれなかった。保護者からは、「先生への感謝の心もある。子供は学校が大好きだった。じゃあどうしてこうなったのか。あまりに鈍感じゃないのか。学校にいれば守られて、安心だったはずなのではないか」との問いが投げかけられた。苛立ちのあまり、「逃げようとばかりしている」「ごまかすな」などの怒号も飛んだ。
「被災時にすぐ現場に行かなかったこと、捜索に当初から参加しなかったことについて、お詫びしたい。遺族を訪問しきれていないことにもお詫びします。これから回ります。行方不明の児童六人、先生一人を継続して捜索もします」
保護者からの矢のような視線を浴びながら、柏葉照幸校長はか細い声で弁明した。
「危機管理マニュアルでは、外にいるときは体を低くするように、校内では机の下に入るように定めていました。校庭に避難して終了としていましたが、堤防を越える津波の場合は高台に逃げるほかありません......。次回の防災訓練では、災害時に保護者に子供を引き渡す『引き渡し訓練』もやる予定でした......」
その後も質疑応答が続いたが、学校側があらかじめ終了時間と決めていた「午後八時」を回ると、司会進行役の大川小の教頭が「もうこの辺で......」と繰り返し、八時半過ぎには打ち切ってしまった。保護者からの「次の(説明会の)予定はあるのか」との問いには、あっさり「ない」と答えた。
説明会が終わった後、会場周辺はもう暗闇に包まれていた。玄関付近で出席者を探し出し、保護者男性に感想を尋ねると「ぜんぜん疑問が解消されねえっちゃ。典型的な事なかれ主義だわ」と吐き捨てるように言った。
夫とともに地元の中学校教員でもある佐藤かつらさん(四十五歳)は、六年生の次女みずほさん(十二歳)を亡くした。やはり学校側の対応にはどうしても納得がいかない。
「どうしたら責任を認めない方向に持っていけるか。そればかり考えている気がします。県や市のレベルで、公立学校の危機管理に関する教員研修は何度も行われてきたはずなのに、まったく生かされなかったことになります。責任は重いと思います」
自宅は大川小よりも三キロほど内陸側だったので無傷だったが、それでも北上川には近かったため、川を逆流する津波が直前まで到達した。好きだったピアノを一生懸命練習する頑張り屋だったというみずほさんの思い出を語りながら、かつらさんは静かに言った。
「みずほの死を無駄にしないためにも、私たち大人がしっかりと検証して、語り継いでいかなければなりません」
保護者間に「悲しい温度差」
一方で、助かった命もある。大川小に当時二年生の男児を通わせていた母親(三十一歳)は、たまたま車で大川小に迎えに来ていたため、間一髪で連れて帰ることができた。当時の様子を知る貴重な証言者だ。
「二時四十分ごろに学校に着いたのですが、間もなく巨大な揺れが襲ってきました。二時五十分ごろ、先生と児童が次々と校庭に出てきて、間もなく点呼を取り始めました。このとき、先生数人が円形に向き合って話し合っていました。『六メートルだってよ』とか『一〇メートルか?』などと男の先生の声が聞こえてきました。『帰っていいですか』と先生たちに尋ねて、子供を親に引き渡す際の『受け渡し書』に署名をした後、一年生の友達も乗せてあげて三人で急いで逃げました」
途中、道路が陥没している場所があって「戻ろうか」とも思った。でも、偶然にも迂回できる道があったため、自宅に辿り着けたという。
釜谷地区の父親(三十八歳)も、当時五年生の男児を助けることができた。
「事務所で取引先の会長と話をしていたら、突然ぐらぐらっと激しい揺れが来ました。急いで従業員を帰宅させて、近所の家の窓を開けて『逃げろ』と言って回りました。三時十五分ごろに車で事務所を出て、北上川を見ると、川の水がどんどん引いていくのが見えました。三時二十五分ごろ、学校にいた子供を乗せて出発すると、新北上大橋に津波がぶつかり、乗り越えようとしていました」
この後、波と競争しながら山の上まで車を走らせ、すんでのところで逃れることができたという。だが、この父親は、大川小のケースは「あくまでも天災」だと強調した。
「釜谷は三〇〇年以上、津波が来ていなかったと言われた地区で、五〇年前のチリ地震津波でも被害はなかった。津波への警戒心は薄く、実際に地元住民も多数亡くなっているんです。あの裏山は急斜面で、低学年の子では登れないと思います。私も息子も、たまたま助かっただけです。先生も死なせたくはなかったはずです。昔からの顔見知りばかりの集落の保護者の間に、悲しい温度差ができてしまったのは本当に残念です」
私はこの後、釜谷地区から一〇キロほど西に進んだ地区にある避難所を訪れてみた。ここでは約五五〇人が避難生活を送っていた。浮津美和恵さん(四十四歳)は、当時六年生の女児を車で連れて帰った一部始終を語った。
「地震の揺れが尋常ではなかったので、すぐに自宅を出発し、道路の亀裂を避けながら走って、三時少し前になんとか学校に辿り着きました。学校はまだ落ち着いた様子でしたが、校庭にいた娘は恐怖で泣いていました」
道すがら聴いていた車のラジオでは、大津波の襲来を伝えていた。近くにいた担任教員に「六メートルの津波が来ます。逃げてください」と裏山を指差して促した。だが、担任は「落ち着いてください」と言うばかりで、行動を起こそうとはしなかった。
結局、担任に「周りの子が動揺するので、先に連れて帰ってください」と言われたので、三時五分ごろ、来た道とは別のルートを通って一〇分ほどかけて北上川沿いの自宅に帰った。すると、五、六メートルの高さの土手を越えて津波が押し寄せてきた。慌てて車を再び走らせ、自宅にいたほかの家族と一緒にさらに山の方向に逃げた。家はほぼ全壊し、避難所生活を余儀なくされることになった。
「うちの子は助かりましたが、亡くなった子供とご遺族の気持ちを思うと......親子ともに、みんな仲良くしていましたから......。あのとき、もっと強く山に逃げるように言っていれば、との思いもあります。でも、もう結果論でしかありません」
浮津さんは、言葉少なに胸の内を明かす。ただ、遺族への学校の事後対応については、疑問も禁じえないという。
「最初からきちんとした謝罪が欲しかったのだと察します。みな安全だと思って、信頼して我が子を預けているわけですから......。学校側の保身や打算が見えていたのではないでしょうか。責任の問題はともかく、教訓として分かち合うべきです。人間としての『気持ち』を示してほしいのだと思います」
津波が来る直前、市河北総合支所地域振興課の及川利信課長補佐は、他の五人の支所職員とともに大川小付近にいた。拡声器で避難を呼びかけつつ、海に向かう車一台一台に引き返すよう説得していた。
「地区の人たちは、家の前で立ち話をするなどしてなかなか動こうとしませんでした。『ここまで津波は来ない』と考えていたのだと思います。実際、市の防災計画やハザードマップでも、釜谷での大津波は想定されていませんでした」
しかし、間もなく大津波は襲ってきた。及川課長補佐は大川小のあの裏山にやっとの思いでよじ登り、命拾いをした。六人の職員のうち、一人は津波に流され死亡している。その夜、みぞれが降る寒空の中、一六人が焚き火をして過ごした。大川小の児童三人もいて、ずっと押し黙り、憔悴しきった表情だった。助かった大川小の教員も見かけており、小さくなって疲れ切った様子だったという。
「あれだけの津波は想定していなかったにしても、海沿いに位置し、裏山の斜面も急な、もっと条件の悪い近隣の相川小、雄勝小の二校では、三階まで波を被りながら、学校にいた児童全員が山に登って無事でした。あの裏山は、子供が登れない斜面ではありません。倒木も見当たりませんでした」
過去には賠償認めた判例も
私はもう一度、大川小を訪れた。裏山は一部を除いてさほどの傾斜はなく、多少の雪があったとしても、子供でも十分に登れるように思えた。釜谷地区全体の死者・行方不明者数は、全住民の四割の約二〇〇人に及ぶ。津波を見ようと堤防に行って流されたり、在宅のまま犠牲になった人も多かったという。あのとき、やはり大人たちに油断と判断の誤りがあったのだろうか。
大川小は現在、市内の別の小学校に間借りして授業を続けている。校長に何度も取材を申し込んだが、その間借り先の小学校教頭が代弁し、「取材要請については校長に伝えたが、コメントは差し控えたいと言っている」と断ってきた。
石巻市教委は、大川小のケースについて次のように説明した。
「学校に避難しようとする地域住民への対応、保護者への引き渡しに手間取り、先生たちがすぐに避難行動に移れなかった面がある。海沿いの多くの学校で決まっていた二次避難場所が、大川小になかったのは問題だった。ただ、校庭への一時避難を行うなどの対応はとっているので、全面的に非があるとは認められない。ただ、遺族の心情は理解できる。一つ一つ誠意をもって対応するしかない」
小学校教員の人事権を持つ県教委にも取材したが、「県としても関心が高い事案だが、まずは市教委の判断、報告を待つ。こちらとして校長の処分などは考えていない」との返答だった。
後日、私は行政訴訟に詳しい知人の弁護士に、大川小のケースについて尋ねてみた。すると、業務上過失致死傷罪などの刑事事件の立件については「刑法ではあくまでも個人の注意義務違反などを対象としている」として可能性は低いとしたものの、民事訴訟は可能だとの見方を示した。
「一五年前、北海道で起きた豊浜トンネル岩盤崩落事故では、犠牲者の遺族に対し、行政の説明不足や不適切な事後対応についての慰謝料を認めて、国に賠償命令を下す判決が後に出ている。これは従来はなかったケースだった。ほかの事故や災害についても、同様に賠償が認められた事例がある」
百か日法要の六月十八日、大川小の合同供養式が市内でしめやかに営まれた。三五〇人が参列し、保護者らは遺族会結成を決めた。
供養式の後、ある遺族は「死亡・行方不明となった児童の保護者のうち、七割ぐらいはまだ納得していないと思う」と打ち明けた。「ここは六年前に石巻市と合併した旧河北町の辺境の小規模地区。『学校側を批判するのは、金が欲しいからだ』と集落内で邪推されるのが一番怖い。だから口をつぐんでしまう遺族もいる」と訴える保護者もいた。
「百か日を機に前へ歩み出したい」「子供はもう帰ってこないし、誰も責めたくはない」などとして、責任追及を避けようとの声があるのも事実だ。だが、不満を募らせる遺族らは、徹底検証のための第三者機関の設置などを求め、県知事、国への要望のほか、市への提訴も検討し始めている。
微妙な心情のずれが見え隠れする。大川小は前身の釜谷小学校が一八七三年に創立されてから、一四〇年近い歴史を持つ。地域のシンボルだった学校を取り巻くコミュニティーの絆に亀裂が入ることは、最も懸念されることだろう。
津波は不可抗力だったとの見方がある。現場にいた教員は全力を尽くそうとしたと信じたいし、そのほとんどが犠牲になった事実も重い。けれども、学校で起きてしまった結果への責任はあまりに重大だ。マニュアルの不備や、「五一分」の間に取った行動が最善でなかったことも明らかだろう。遺族たちは、なお悔やんでも悔やみきれない心境に沈んでおり、心のケアも求められている。未来を断たれた子供たちのためにも、そして二度と同じ悲劇を繰り返さないためにも、学校側は「何が起こったのか」をしっかりと刻印し、目に見える形での「けじめ」をつけるべきではないだろうか。(了)
〔『中央公論』2011年8月号〕