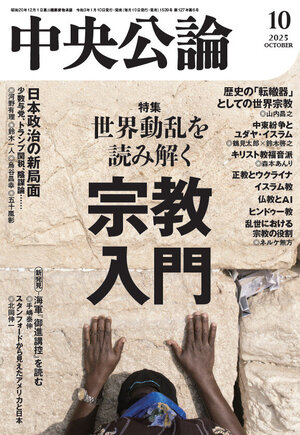織田信長も切り取った蘭奢待、14年ぶりに公開
信長の蘭奢待切り取りをめぐる評価
いま同時代の史料にもとづき紹介してきた一連のできごとは、〝信長が天皇家の宝物である蘭奢待を切り取った〟行為として、その意義を問う研究が多くなされた。戦前では、「自(みずから)、天下の覇者を以て任ずる意志を表示するにあらずして何ぞや」(中村孝也(こうや)氏)、「蘭奢待の切取勅許は信長にとりては至大の名誉にして此時既に天下を掌握し足利氏に代るの形勢を示せり」(渡辺世祐(よすけ)氏)のような見方が代表的なものである。
さらにその後も、天皇家の宝物を切り取るという行為を、当時の正親町天皇に向けた示威、圧力のように捉える研究が優勢で、天皇も信長の申し入れに不満を持ち、信長と天皇・朝廷が対立していたことを示す象徴的な事件として理解されてきた。
しかしわたしは、信長と天皇が対立していたとする見方に疑問を呈する研究をふまえて一連の史料を検討した結果、右のようには考えられないことを論じた。
信長は威圧的に天皇や奈良の人びとに接したわけではなく、手続きにのっとり、開封の作法に従った。引き連れた軍勢(三千人)にも、駐留時に住民に迷惑をかけないように命じ、東大寺などを訪れたさいにもきちんとお詣りをして相手を尊重する姿勢をみせた。
いっぽう、蘭奢待拝見を請うた信長に天皇が不満を表明したとされていた史料を再検討し、実は不満の主は天皇ではなく、このときの手続きに対する天皇の対応に苦言を呈した公家であり、信長と天皇に対立的な関係はないことを明らかにした。
突然の申し入れであり、蘭奢待を外に持ち出すなど異例ずくめであったとはいえ、〝奈良に乗りこんで無理やり切り取った〟かのように思われてきたこのできごとは、強大な権力者・織田信長という像によりゆがめられて理解されてきたのである。
小稿の副題にあるように、「あの信長も切り取った」という決まり文句が冠せられるのも、このような歴史像に起因すると思われる。
*
ここまであれこれと蘭奢待について書いてきたけれども、わたしはこの香木の実物を目にしたことがない。14年前がその好機であったが、残念ながら奈良を訪れることができず、観に行った知り合いにお願いして蘭奢待のキーホルダーを買ってきてもらっただけに終わった。今年を逃せば、生きているあいだに観ることは叶わないかもしれない。そんな悲愴感を抱きながら、拝見することをひそかに心に期している。
(『中央公論』10月号では、蘭奢待という呼称の由来、足利義政・明治天皇による切り取りの状況、蘭奢待切り取りの意味などについて論じている。)
[参考文献]
金子拓『織田信長権力論』(吉川弘文館、2015年)
同『織田信長〈天下人〉の実像』(講談社現代新書、2014年)
工藤三壽男「正倉院御物〝蘭奢待〟と岡谷繁実」(『歴史研究』392、1994年)
杉本一樹『正倉院』(中公新書、2008年)
東京大学史料編纂所編纂『大日本史料』第八編之三十五・第十編之二十一
ドナルド・キーン(角地幸男訳)『明治天皇(二)』(新潮文庫、2007年)
中村孝也『日本近世史 第一巻』(育英書院、1916年)
米田雄介「正倉院宝物の保存--徳川家康公の事跡と関連して」(『大日光』67、1996年)
和田軍一「らんじゃたい」(『日本歴史』335、1976年)
渡辺世祐『訂正増補大日本時代史 安土桃山時代史』(早稲田大学出版部、1916年)
1967年山形県生まれ。東北大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。専門は日本中世史。『記憶の歴史学』『織田信長〈天下人〉の実像』『鳥居強右衛門』『信長家臣明智光秀』『長篠合戦』など著書多数。