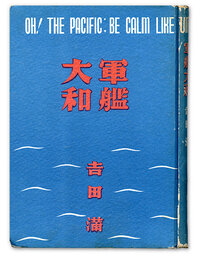震災前に"逆戻り"する永田町 与野党ともに党内論議こそ急務
三月十一日に東日本大震災が発生後、少しずつではあれ復旧が進むかと思いきや、四月七日深夜にはマグニチュード七を超える余震が被災地を襲った。今後さらに巨大な「余震」が発生する可能性もあるという。今論じられるのは、地震の後ではなく、地震の中で何が起こるかである。
歴史をひもとけば、関東大震災が起こったのは、一九二三年九月一日。翌二四年一月十五日、政治学者の吉野作造は日記にこう記している―「朝五時五十分飛んでもなき大きな地震あり。此前程ではないが余震としては大変なヤツ也。被害も多かるべく思はる」。
大震災後に余震が襲うのは、今も当時も同じであった。地震は一回きりではない。人々は繰り返し襲ってくる地震とともに長い時間を生きることになる。
とはいえ、余震の中では、地震の恐怖におびえ続けるわけではない。二四年一月の地震の日、政治家の日記を見ると、地震の記述はほとんどない。震災からの復興計画を掲げた後藤新平を内相とする山本権兵衛内閣は、青年が摂政を狙撃した虎ノ門事件で総辞職し、後任の首相に枢密院議長の清浦奎吾が就任した。ながらく多数党だった政友会は清浦内閣支持派と反対派に分裂し、反対派は憲政会・革新倶楽部による、普通選挙と政党内閣を掲げる第二次護憲運動に加わった。数ヵ月後の総選挙では護憲三派が大勝し、加藤高明内閣が成立して、政党内閣時代が幕を開ける。政治家の関心は揺れ動く政局そのものだった。
政治史が記憶するのは、こうした特権内閣の成立に対する政党側の対抗運動というストーリーである。震災が護憲運動を呼び覚ましたとは解釈しない。震災後の動揺は、様々な形で政治に跳ね返っていたとしても、である。
最近のメディアでは、今回の東日本大震災をきっかけに日本の政治と社会が変わるという論調が多い。だが、政治は行きつ戻りつを繰り返すであろう。震災とともに政治は変わるが、震災そのものによってではなく、その後の出来事の連鎖によって変わったと記憶されるからである。
震災直前、菅直人内閣は崩壊寸前であった。予算成立の見通しは立たず、閣僚の外国人献金問題で首相自身辞任寸前だったように見えた。そこに訪れた震災により、被災者の救援と福島原発事故への対応が緊急の課題となった。それまで政権が見定められていなかった政策課題の中で、優先順位が明らかになった。これにうまく自民党などの野党を巻き込めば、政治の転換が訪れたのかもしれない。
しかし、官僚組織を使いこなせず、失言とも気づかずに首相の発言をメディアに流すような内閣参与を抱え、大連立を申し入れた谷垣禎一自民党総裁を怒鳴りつけるといった首相と官邸の振る舞いは、明らかに指導者としての資質を欠いていた。その上で民主党は、統一地方選挙前半戦で惨敗し、二〇〇九年の総選挙でつかみかけた多数党としての権力基盤を地方で固めることに失敗した。もはや民主党は、次の総選挙で世論の「風」を頼むしか勝ち目が無くなったとさえ言いうる。それを見透かしたかのように、自民党と公明党は、政権批判を強めている。まるで震災前に逆戻りしたかのようである。
これは確かに憂慮すべき事態である。だが、この抜き差しならない構図を少しずつ壊していくのが、繰り返し襲いかかる余震や原発の新展開であろう。加えて、二年後には衆議院議員の任期切れが来る。各党は、次の総選挙から逆算して態勢を固めるときにさしかかっているのである。
民主党政権に必要なのは、まずは、もっとも強みとしたはずの情報公開を的確に進めて、原発の状況を即時にメディアに伝えることである。そして、復興プランと次の総選挙をにらみつつ、マニフェストを全面改変することであろう。ついで、自民党・公明党に必要なのは、財界や地方との関係を十分に生かしつつ、党内論議を経た政策案を掲げ、それをもとに復興予算の交渉に臨むことである。たとえば、具体性のある自民党の緊急提言は、将来の自民党のマニフェストの準備作業になりうるであろう。
また、いまだ野党の協力を確保できていない段階で、復興構想会議がどこまで実効的になりうるかは不明だが、与野党の距離を縮める役割を果たす可能性は十分にある。いかなる復興ビジョンが望ましいか、与野党は、安易な大連立よりは国民の目に見える党内論議を重ねるべきである。そうした試行錯誤を通じた接近こそ、将来の政党政治を安定させるためには不可欠なのである。
(了)
〔『中央公論』2011年5月号より〕