「試験の公平性」だけ追求していればそれでいいのか?
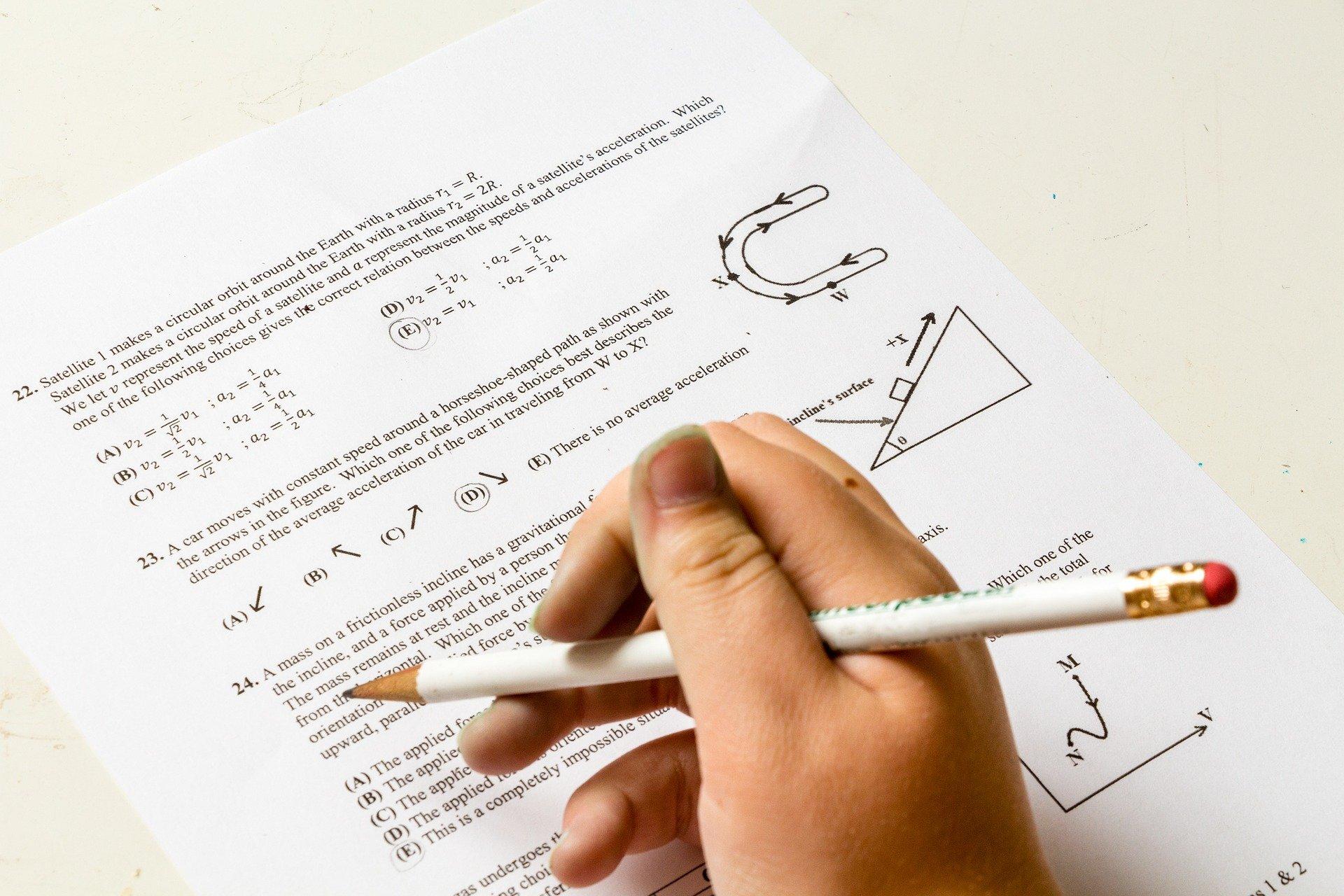
※本稿は橘木俊詔『大学はどこまで「公平」であるべきか』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。
■50%を超えた大学進学率だが
文部科学省の統計『令和元年度学校基本調査』によると、2019年の日本人の大学(学部)進学率は53・7%。短大を含めれば、その進学率は58・1%、ほぼ6割にまで達していることが分かる。
1980年代の大学進学率は30%前後に留まっていた。しかし平成に入ってから、女子学生の増加とともに右肩上がりで上昇。90年代後半には大学・短大進学率の合計が50%台に突入し、大きく下がることなく今に至っている。
都道府県別で見ると、1位の京都府が65・87%、2位の東京都が65・13%、3位の兵庫県は60・90%、4位神奈川県60・70%であるのに対して、44位が鳥取県の43・31%、45位が鹿児島県の43・28%、46位は山口県43・06%、 47 位の沖縄県40・19%となっている。
なお厚生労働省の『賃金構造基本統計調査の統計データ(2019年度)』によれば、都道府県別年収ランキングのトップテン内に京都府、東京都、兵庫県、神奈川県がすべて入っている。逆に、ワーストテンのなかには鳥取県、鹿児島県、沖縄県が入っている。
このデータを踏まえれば、県民所得の高い府県と低い府県とで大学進学率にはある程度の相関関係があり、大学進学率は家計所得によって左右されがちと言えるのかもしれない。
しかし『大学はどこまで「公平」であるべきか』でも詳しく記したが、昨今の入試改革では、こうした意味合いでの「公平さ」はほとんど語られることがないまま、ここまで進んできた(そして今も触れられていない)印象が強いことはここに追記しておく。
■ようやく先進国並みとなった日本の大学進学率
一方で「Education at a Glanceʼ2019」をデータソースとしてOECD加盟国に注目すると、そのデータの2012年度版を比較資料とすることで、大学型高等教育への進学率を知ることができる。
これによると、日本は51・6%。OECD加盟国の平均が58・3%なので、平均よりやや低いことが分かり、世界でも目立つほどの高学歴社会とまでは言えないのかもしれない。
ちなみに主要諸国では、アメリカ71・2%、韓国68・5%、イギリス67・4%、ドイツ53・2%、フランス40・8%であり、アメリカと韓国は既に大学卒業者が多数派の国ということが分かる。
大学の定義は国によって異なるので細かい国際比較は困難でもあるが、ともあれ、ようやく日本も他の先進国と比較して遜色のないレベルの大学進学率を備えつつある、ということは言えそうだ。
■高まった大学進学率の先で
ではここまで高まってきた大学進学率の先で、日本の大学はこれまで十字架のように背負ってきた「公平さ」をどう考えるべきなのか? 令和となり、グローバル化が進む今でも、戦後から連綿と続く「一発試験で選抜した少数エリートを育てる」という姿勢のままで本当によいのだろうか?
そもそもだが、大学は大きく言って教える側の教授、学ぶ側の学生、それに事務をつかさどる事務職、そして管理と政策を担当する文部科学省という四者によって構成されている。
それぞれが大学という学問の場を支える役割を担い、今、激変への対応を求められているわけだが、ここでは特に学生に着目して論じたい。日本の未来を担う学生たちに、この先大学はどう向きあうべきだろうか?
■日本の大学教育に足りないもの
日本の大学で学生を教育する上での最大の問題は、学生が勉強しないこととされてきた。その責任は大学にもあって、大学が学生を厳格に教育して、高い学識と技術を身につけさせ社会に送り出そうという思想と熱意に欠けている点が指摘される。
実際、一昔前は「大学はレジャーランドである」とまで言われ、大学には勉強するためではなく遊びに来る学生たちや、彼らの勉強意欲を引き出そうとするでもなく、つまらない授業を続ける教師たちの姿に批判的な声が上がった。
しかし大学そのものが競争にさらされる中で、さまざまな制度が導入され、多くの改革が施され始めた。そのため「レジャーランド」と揶揄された当時ほどは酷くはないだろうが、それでも大学卒業が容易ではない欧米と比較すると、大学側の教育にかける熱意やその根底をなす思想や方針において、日本の大学教育のありかたはまだ見劣りする印象がある。
だからこそ『大学はどこまで「公平」であるべきか』で詳しく述べたように、筆者の案としては教育に熱意を抱く、教育に特化した教授が増え、彼らが中心となって優れた教育を行うことを期待したい。
■純粋学問をどこまで追求すべきか
また、以下も同書で指摘したことだが、日本の大学教育には旧帝国大学の伝統が未だに残っていて、純粋学問を研究・教育するのが大学の役割と大学人側が思っており、旧来の学問(法律、経済、文学、理学など)を偏重し、社会に出て働くときに役立つ実学をさほど教えない傾向もみられる。
その例外は医学・薬学・工学・農学で、これらの学部では卒業後の仕事に役立つ学問を教えている。問題はこういった学部で学ぶ人の数がそもそも少なく、大半は先に述べた伝統的な学問の学部で、さほど勉強もしないまま卒業していくことにもある。
しかし大学進学率が5割以上に達し、その多くが研究者などではなく、一般の会社員などとして人生を送ることが予想される現在、純粋学問を果たしてどこまで追求すべきか、急ぎ、再検討が必要だろう。むしろ、大半の学生には、社会に出てからうまく仕事をこなせるような実学を施すことをより意識するべきなのではないだろうか。
そうすることで、無味乾燥な学問を勉強して意欲を失うかわりに、卒業後の仕事のことを考え、真剣に勉学や技能訓練に励むようになると予想できるからだ。また学生側も、そこで蓄積した能力や経験、適正の見極めのおかげで、社会に出た後などに、求められる力と自らの力とのギャップに苦しむ機会がかなり減るはずである
■会社も社員を育てる余裕がなくなった時代に
そういった再検討が必要とされる背景として、多くの学生が大学卒業後に就職するであろう、企業側の変化も大きい。かつてであれば、入社後に新入社員らを教育し、訓練する余裕も風土も企業にあったし、入社するにあたって、学生にそこまでの知識や技能を求めてはいなかった。
しかしその資金や育てるだけの時間がないほどに競争が激しい時代となり、企業が即戦力を望むようになったという事情もある。
いずれにせよ今必要なことは、教える側も実学で学生を鍛えるという強い意思をもち、一人前の職業人を育て上げるという気概で教育にあたることである。
もともと日本の専修学校はこのような実学教育をしており、職業教育の一環としてかなり重要な役割を果たしてきた。これだけ多くの学生が大学進学する現代、その精神なり教育方法を早急に大学でも導入するべきではなかろうか。
橘木俊詔
教育機会の平等・均等路線の先で混迷を極める入試改革。著者はその状況に「繕われた公平さに意味などない」「世界で通用する大学やエリートを生み出せるのか」と警鐘を鳴らす。進学率が5割を超えて、最早エリートのためのものではなくなった大学はこの先どんな存在であるべきか? 未だ詰め込み型の「一発入試」に頼る大学に創造性ある学生を選ぶことはできるのか? 「公平」という呪縛から逃れなければ、大学に未来はない!














