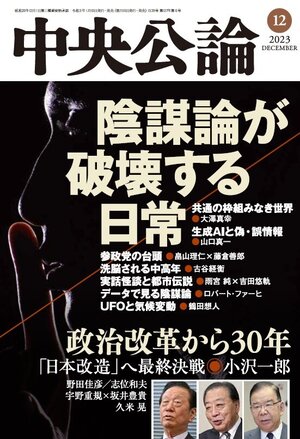『わが谷は緑なりき』監督:ジョン・フォード 評者:三浦哲哉 【気まぐれ映画館】
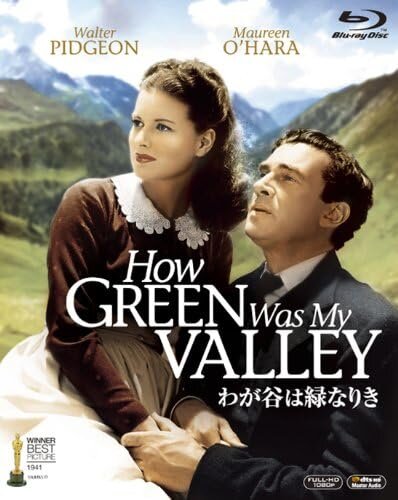
評者:三浦哲哉(青山学院大学教授)
1年間担当した連載も今回が最後なので、シンプルに、自分が最も好きな映画を取り上げたい。『わが谷は緑なりき』(1941)だ。最も好きな、というより、映画に真の意味で入門するきっかけとなった一本だ。
初めて見たのは1990年代後半の渋谷の映画館。フォード特集をやっていた。卒倒するほど感動し、ふらふらと映画館を後にした。
原作はリチャード・レウェリンのベストセラー小説。主人公ヒュー・モーガンが、炭鉱町で過ごした自分の少年時代を回想する。とにかく全篇がうつくしい光で充たされた、文字通り宝石のような一本だ。
とくに圧倒されるのは、回想される過去の世界へ、話者のナレーションとともになだらかに入ってゆく導入部分だ。決定的なシーンがある。
「ヒュー!」
と、姉のアンハード・モーガン(モーリン・オハラ)が独特の節をつけて、丘の斜面のはるか先にいる主人公ヒューに呼びかける。
「アンハード!」
と、弟がよく通る声で応じる。
私はここでいつも涙腺を決壊させてしまう。まだ開始数分しか経っていないというのに。
このとき画面は、奥へ奥へと、どこまでも視線が吸い込まれそうな縦構図(手前と奥のあいだの、スクリーンに対して垂直=縦の線が強調された構図)。手前にはアンハード。奥にはヒュー。さらにその奥に、丘の木々がぼんやりと白く霞みながら穏やかに輝く。監督フォードは、観客の視線を吸引せずにいない、画面の奥行き表現にも天才を発揮したが、ここはそのきわめつきの一例だろう。この手前と奥とで、声が行き来する。「ヒュー」と呼ぶ声は届き、「アンハード」と呼ぶ声が戻ってくる。
かつて習慣的に交わされた、姉との懐かしい声のコール&レスポンスを、主人公がその光景とともに鮮やかに思い出している──。そう理解して済むのではなく、何か異様な感動がある。
過去に触れている、というあまりに生々しい印象を私たちは、ここで期せずして受け取る。いや、懐かしくてたまらない過去の遠さそれ自体が、触れられるほど具体的な何かとして、目の前に在る、と感じる。本当に不思議だ。過去と現在の距離そのものを、見て、感じているというような。今も、見るたびに茫然自失としてしまう。映画が精神的な時間旅行を可能にする媒体であるという事実を、おそらく私はこの場面を見たときに初めて直感したのだろう。名作を一本見た、という以上の意味があった。
このあとに描かれる場面もあまりにうつくしい。街中総出の結婚式。こだまする男たちの合唱。肝っ玉母さんの仁王立ち。花咲く丘の上への遠出。誇りをかけた少年たちの拳闘。炭鉱事故とその悲痛な帰結......。うつくしさの印象は、これらが、召喚された、今はなき過去の記憶だということが、冒頭の呼び声ではっきりと示されることによる。それゆえ、これらの光景が、輝いて感じられるのだ。
(『中央公論』2023年12月号より)