『科学文明の起源――近代世界を生んだグローバルな科学の歴史』ジェイムズ・ポスケット著/水谷 淳訳 評者:松村一志【新刊この一冊】
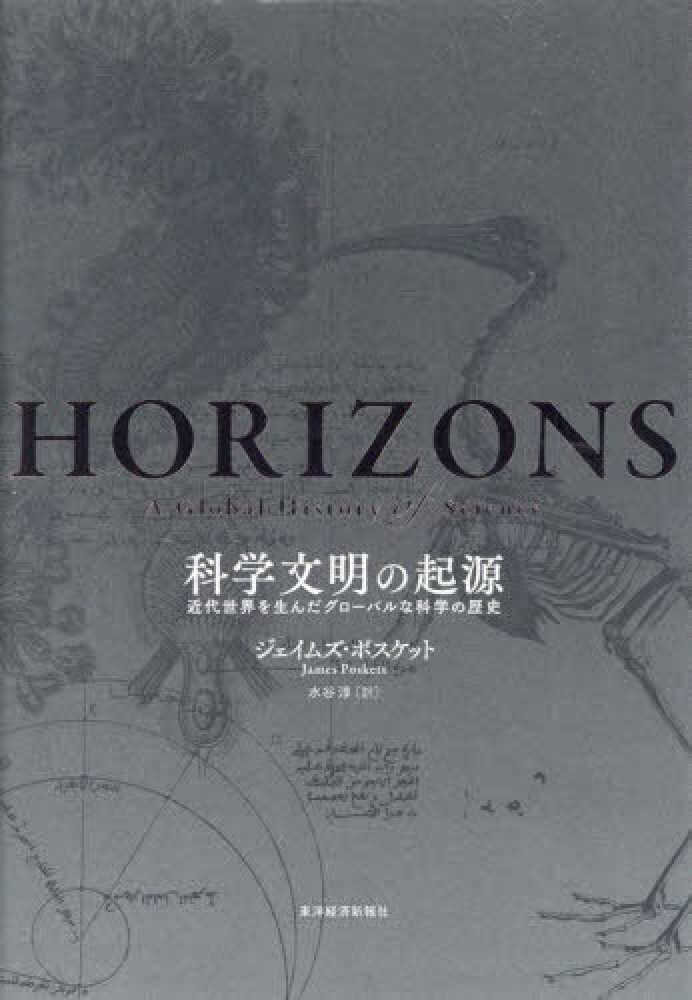
評者:松村一志(成城大学専任講師)
科学はヨーロッパの産物である──近代を生きる私たちにとって、このことは強固な常識となってきた。科学史家ジェイムズ・ポスケットの『科学文明の起源』(原題Horizons)は、この常識に挑戦した好著である。
科学史の最大のトピックの一つは、「科学革命」と呼ばれる知の地殻変動だろう。その古典的な説明では、16世紀から17世紀のヨーロッパにおいて、古代や中世の科学とは大きく異なる近代科学が出現したとされる。例えば、機械論的世界観の成立や、観察・実験の重視などがその特徴である。
本書は、この種の考え方をヨーロッパ中心主義として否定していく。代わりに導入されるのが、グローバル・ヒストリーという観点だ。それは、従来の地域区分に囚われない超域的な歴史記述のことである。例えば、ヨーロッパの出来事を中東やアフリカといった他の地域との繋がりの中で考えていく。
近年の科学史では、そうしたグローバル・ヒストリーの手法を用いた研究が進められてきた。本書はその成果をふんだんに取り入れることで、「科学革命」やそれに続く近代科学の重要なエピソードを、言わばオセロのように次々とひっくり返してみせる。
最も象徴的なのは、コペルニクスの地動説だろう。地動説の登場は、近代科学の始まりを告げる出来事として語られてきたが、実を言うと、コペルニクスの『天球の回転について』にはイスラムの著述家も引用されている。イスラム世界は古代ギリシアの知識を継承しており、当時のヨーロッパの学者の間でもイスラムの天文学が受容されていた。その意味で、ヨーロッパとイスラム世界の文化交流こそが、地動説を可能にしたのだと著者は言う。
こうした意外なエピソードが、本書ではいくつも紹介されていく。例えば、ニュートンの『プリンキピア』が南米や西アフリカで行われた実験の結果を論じていたことや、ダーウィンの『種の起源』がそれに先立ってロシアや中国で議論されていた進化論に言及していたこと、また20世紀初頭の現代物理学の発展にロシア、中国、日本、インドの科学者が大きく貢献したことなど、通常は見落とされがちな出来事が並べられるが、その中から、グローバルな交流の産物としての近代科学の姿がくっきりと浮かび上がってくる。
ただし、本書はグローバリゼーションを言祝(ことほ)ぐものではない。グローバリゼーションは幸福な出合いをもたらすこともあるが、近代科学の歴史はむしろ、奴隷制と帝国主義、産業資本主義とナショナリズム、イデオロギーと戦争が生み出す搾取と背中合わせだった。21世紀の科学もその延長線上にある。
一口にグローバルな交流と言っても様々な形態があり、思わぬ帰結を伴う。そう考えると、グローバリゼーションのもたらす多様な出合いのあり方を歴史の中から学び取り、それに照らして、いま何が起きているのかを考え続けることが必要だろう。本書で紹介されるエピソードの数々は、そのための貴重な手がかりになる。
ところで、本書との出合いもまた、グローバルな交流の一幕である。本文だけでも450頁と分厚いが、一般読者向けに書かれており、読みやすい。著者の語り口もさることながら、水谷淳の平明な訳文によるところも大きいだろう。その意味でも、多くの読者に読まれ、検討されるべき一冊だ。
(『中央公論』2024年3月号より)
◆ジェイムズ・ポスケット〔James Poskett〕
ウォーリック大学准教授。専門は科学技術史。インドの天文台からオーストラリアの自然史博物館まで、世界各地を調査のために訪れている。著書に『Materials of the Mind』(未邦訳)。
【評者】
◆松村一志〔まつむらかずし〕
1988年東京都生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。専門は社会学、科学論。著書に『エビデンスの社会学』。













