『民度─分極化時代の日本の民主主義』善教将大著 評者:石戸 諭【新刊この一冊】
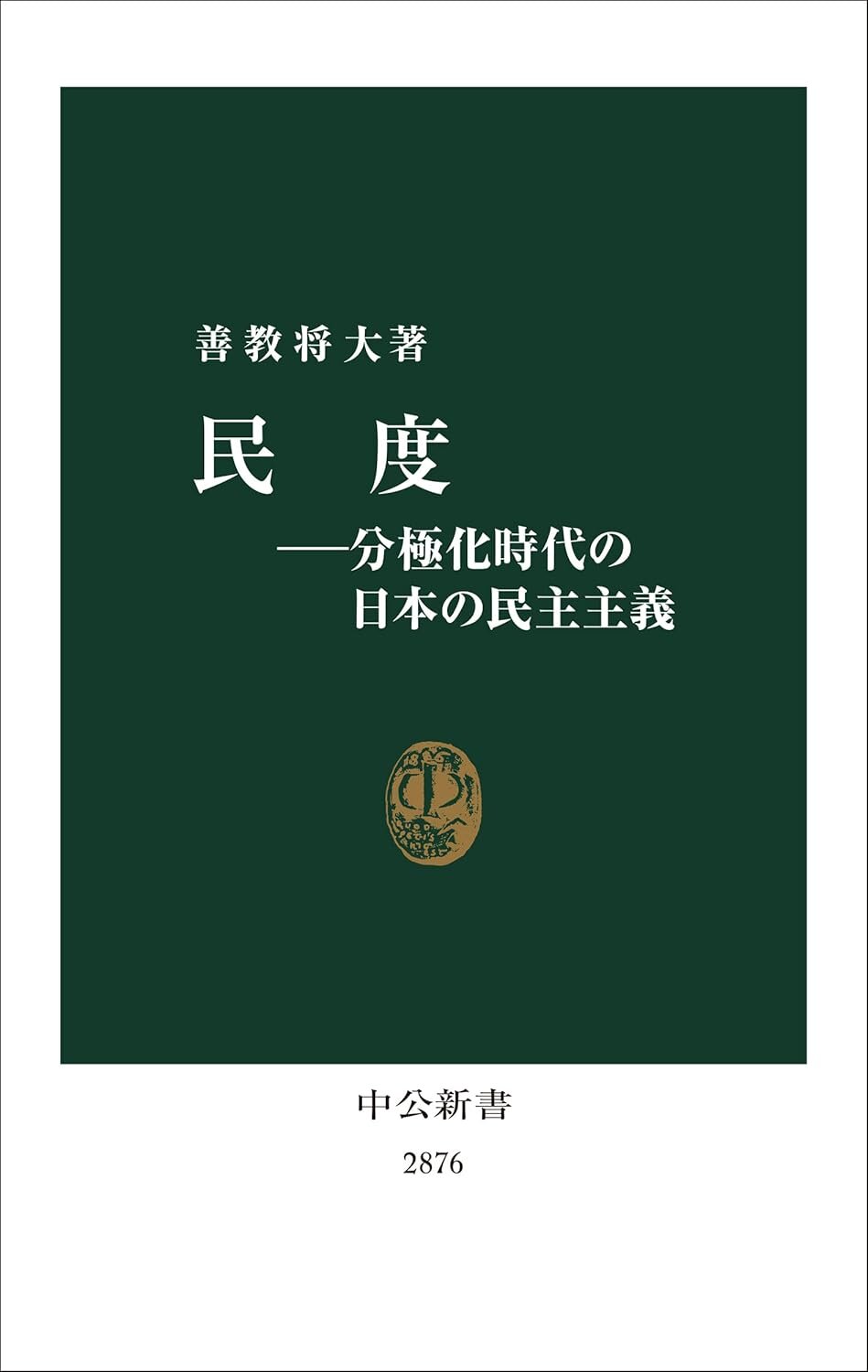
評者:石戸 諭(ノンフィクションライター)
「民度が低い!」――昨今、こうした声を選挙取材のたびに聞かされてうんざりしていた。名指しされるのは特定の政党に投票した有権者だったり、ある地域の住民だったりする。訴える人々は総じて正義感に満ちているのが特徴だが、はたして「民度」とは何か? 例えば、高市政権と「閣外協力」をする日本維新の会が小選挙区で勝利を収めている大阪府民は民度が低いと指摘する人々がいる。彼らが想定する民度が高い状態とは何を意味するのか。
本書のエッセンスを私なりに抽出しておくと、「民度」という言葉そのものが、それを使用する人々の党派性と結びついた言葉であることが重要なポイントだ。例えば維新に拒否感を抱く人々は、維新支持層が多い地域を民度が低いと判断している。自民党支持層は自民支持者が多い地域を民度が高いと評し、共産党支持層は最も敏感に同じ傾向を示す。「民度」は左派系がやや好んで使う傾向にあるようだが、どちらにしても自分が好む政党が支持を得るか否かが大きな要素を占める。
したがって、選挙のときに多く見られるように投票率を「民度」と結びつけることには慎重でないといけない。善教も強調しているが、投票率の低下は世界的なトレンドだ。私が仕事をしてきた日本のメディアでは選挙のたびに啓発的な記事が量産されてきた。そこで前提となるのは、やや強い表現になってしまうが、日頃から政治に関心を持って投票に行く有権者こそ望ましい有権者であり、投票に行かないことは権利を捨てる恥ずべき行為であるという意識だ。こうした前提に立つ限り、投票率の低下は「民度が低い有権者の増加」という結論しか導けない。
だが、本当にそれは有効な認識なのだろうか。本書で最新の知見をもとに論じられているように、世界的にも世代交代によって「投票を義務」だと捉える有権者は減少している。日本では、1990年代に進んだ選挙制度改革が投票率の低下をもたらした可能性が示唆される。特に非都市部において、政党や政治家の動員力を低下させる効果があったという。つまり有権者の意識低下よりも、制度がもたらす弊害が本質的な課題である。これは政治課題として急浮上した議員定数削減問題とも密接にかかわる知見だ。
民度にまとわりつく「党派性」は2020年代の日本政治を動かす大きな要因になるだろう。人間である以上、感情と無関係であることは避けられない。政治に関心が高まり党派性が強くなれば、嫌いな政党を利する言説よりも、陰謀論的であろうと批判する声の方を心地よく受け入れる傾向はより強まっていく。参政党支持者は陰謀論を支持している、と批判する左派系の人々が、別の陰謀論は好意的に受け入れることが典型だ。
私を含め、メディアで報じる者に必要なのは、「民度」を人々の意識の問題として片付けるのではなく、専門的な知見を積極的に取り入れ、多様な民意─無論、投票を棄権する人も含めて─から「民度」を深く理解しようとする営みだろう。党派的で分極化を促す旧態依然とした批判的ジャーナリズムから、分析的かつ包括的で、理解をもとに適切な論や批判を多彩に展開するメディア環境へ。本書で的確に示されたエビデンスをもとに、変化の方向性は見えてきた。
(『中央公論』2026年1月号より)
◆善教将大〔ぜんきょうまさひろ〕
西学院大学教授。1982年広島県生まれ。立命館大学大学院政策科学研究科博士後期課程修了。博士(政策科学)。専門は政治行動論、政治意識論、意識調査方法論。著書に『維新支持の分析』、編著に『政治意識研究の最前線』などがある。
【評者】
◆石戸 諭〔いしどさとる〕
1984年東京都生まれ。立命館大学法学部卒業後、毎日新聞社に入社。その後、BuzzFeed Japanを経て独立。著書に『「嫌われ者」の正体』『昭和ノンフィクション名作選』など。













