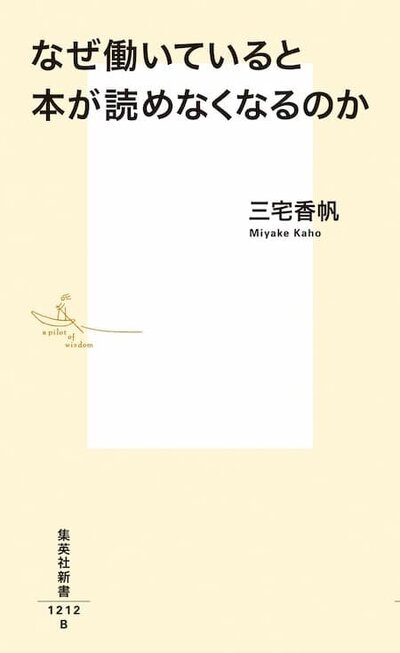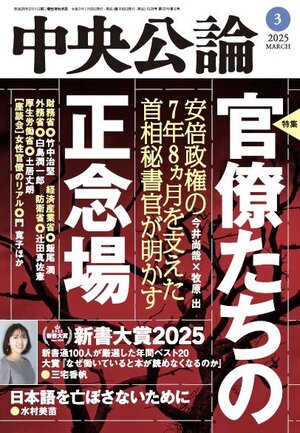これからも「名付ける責任」を担いたい <新書大賞2025>大賞受賞『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』三宅香帆氏インタビュー

これからも「名付ける責任」を担いたい
――大賞受賞、おめでとうございます。新書大賞史上、最年少、初の平成生まれの受賞者です。率直なご感想をお聞かせください。
本当にうれしいです。実は新書というジャンルをもっと盛り上げたいという気持ちもあり、この本のもとになった連載を始めた時から新書大賞を狙いたいと公言していたんです。実際に受賞できてほっとしています。2021年から新書大賞の投票にも参加していますが、連載を新書にまとめる際には、これまでの新書大賞の上位作品や受賞者のインタビューを徹底的に読み込んで研究したのですが、その甲斐がありましたね。(笑)
――受賞作『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(以下、『なぜ働』)はすでにベストセラーになっていますが、ここまでの反響を得られたのはなぜだと思いますか。
やはりみんな、仕事とスマホだけの生活でいい、と思っているわけではないということだと思います。とかく現代人は本よりスマホに夢中になっていると言われますが、実際にはみんなスマホばかり見ていることにうしろめたさを感じる部分がある。さらに、コロナ禍を経て、通勤や残業時間が減って、自分の時間の使い方をもう一度考え直した人が増えたような気がします。その中で読書にかける時間も再考されるようになったのではないでしょうか。コスパやタイパの流行を再考する流れが来ているとは以前から感じていましたが、そうした時代の気分に合ったのかもしれません。
勤めていた会社の元同僚や上司からも、本書の感想をたくさんもらいました。当時の上司からは「本が読みたかったから会社辞めたの?」というメッセージも来ました(笑)。私がいたリクルートは、比較的働くのが好きな人の多い会社でしたが、そういう会社の人にも本書が読まれているのはうれしいですね。
「半身社会」と「ノイズ」
――本書はタイトルの通り、「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」という問いに答えるために、日本における読書と労働の歴史を明治時代から現代まで振り返っています。なによりそのタイトルに惹かれて手に取った方も多いと思います。
私自身、大学院を出て社会人として働く中で、思うように本を読めていないことにショックを受けた一人でした。さらに、4年前にヒットした映画『花束みたいな恋をした』を観たことも大きかったです。学生時代に好きな本や音楽など文化的な趣味で意気投合し付き合ったカップルが主人公なのですが、彼氏が働き始めて仕事が忙しくなるにつれ文化的趣味に興味がなくなるようになり、やがて二人がすれ違うようになる。そのシーンを見て身につまされたと言っている人も多く、「働いていると本が読めない問題」はみんな共通の悩みなのではないかと思ったんです。
いざこのタイトルでいこうと決めたのは、レジーさんの『ファスト教養』(集英社新書)の刊行記念対談記事で話した際です。誰もが日々時間に追われ、教養さえもビジネスで役に立つなどのファストなものを指すことが多くなりつつあるという話の中で、私が「とはいえ、働いていると時間がないし、本が読めないのは仕方がないですよね」とこぼしたら、SNSで記事をシェアしていた方がその部分に強く共感してくれたんです。
その問題意識をストレートにうたったタイトルを提案したら、担当編集者や周囲が思いのほか反応してくれて。その反応を見て、これはみんなの関心を引くタイトルなのかもしれない、と思いました。
(『中央公論』3月号では、この後も受賞作執筆の裏話や、批評家としての今後の抱負などについて話を聞いた。)
「新書大賞2025」上位20冊までのランキングと、有識者45名の講評など詳細は、2025年2月10日発売の『中央公論』3月号に掲載されています。
特設ページでも上位20位までのランキングを掲載しています。
「新書大賞」特設ページ https://chuokoron.jp/shinsho_award/