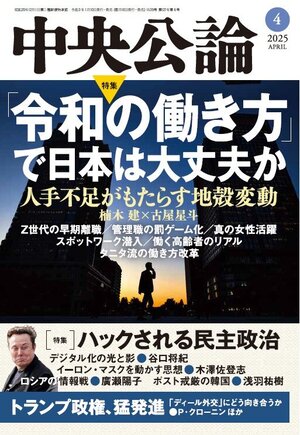人手不足が労働市場にもたらすポジティブな変化
労働市場が動き出す
楠木 マクロの動きを制御するメカニズムとして、法制度はきわめて大事。特に労働については、最低賃金のような制度は絶対に必要だと思います。
ただご指摘のとおり、市場による相互選択というメカニズムも重要。労働市場の流動性は高いほどいいわけではありませんが、今までがあまりにも低かった。つまり、働く側にキャリアを通じて働く場所を選ぶという意識が希薄だったんですよね。働き方に限った話ではありませんが、「自分にはこれしかない」と思い込んで選択肢を持たない状態は、人間にとって非常に不幸で不健康です。自分がより気分良く働ける職場はないかと常に探し続ければいいし、企業側も気分良く働いてくれそうな人材を選べばいい。それを可能にするのが相互選択の労働市場ですよね。その役割は法制度よりはるかに大きいと思います。
僕も大学に常勤でいたころ、常に移籍や転職を頭の片隅で意識しながら仕事していました。そうすると大学側も、何か気に入らないことがあるのかなと意識するようになる。するとお互いにある種の緊張状態が生まれます。そのほうが経営の規律が働きやすくなるんじゃないでしょうか。
古屋 今、転職希望者がすごく増えているんですよね。総務省が発表した「労働力調査」によると、2023年には1000万人を超えて過去最高を記録しました。ところが問題は、実際に転職している人がまったく増えていないことです。
実は転職のメリットはかなり大きいんです。例えば49歳までの転職者の場合、今や給与が減る人よりも増える人のほうが多いという統計が出ている。「35歳限界説」などと言われたこともありましたが、それはもう完全に過去の話です。
では、なぜ転職者が増えないのか。私は〝おせっかい〟が足りないからだと思っています。転職のために自ら行動を起こせる人はいいのですが、今の仕事に不安を抱えながらも、忙しくて動けない人、どう動いていいかわからない人が大勢います。そういう人にどう救いの手を差し伸べるか。それは今後、ハローワークの機能のあり方などを含め、社会として考えるべきテーマだと思います。
(『中央公論』4月号では、この後も「努力の娯楽化」の効用、体育会系の不動産会社オープンハウスの成功、コミュニティとしての職場について詳しく論じている。)
構成:島田栄昭
1964年東京都生まれ。一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。一橋ビジネススクール教授などを経て2023年より現職。専門は競争戦略。企業の経営諮問委員や社外取締役などを歴任。『ストーリーとしての競争戦略』『逆・タイムマシン経営論』「楠木建の頭の中」シリーズなど著書多数。
◆古屋星斗〔ふるやしょうと〕
1986年岐阜県生まれ。2011年一橋大学大学院社会学研究科修了。同年、経済産業省に入省。17年より現職。ひととしごとの研究者として、人口動態から2040年の労働需給を推計した未来予測研究や、次世代のキャリア形成を研究する。主な著書に『ゆるい職場』『「働き手不足1100万人」の衝撃』などがある。