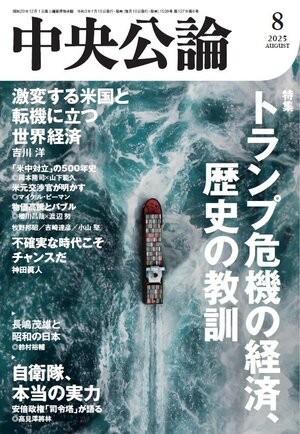原田泰 人口減少でデフレになる? 元日銀審議委員が「奇妙な経済理論」を論破する【著者に聞く】
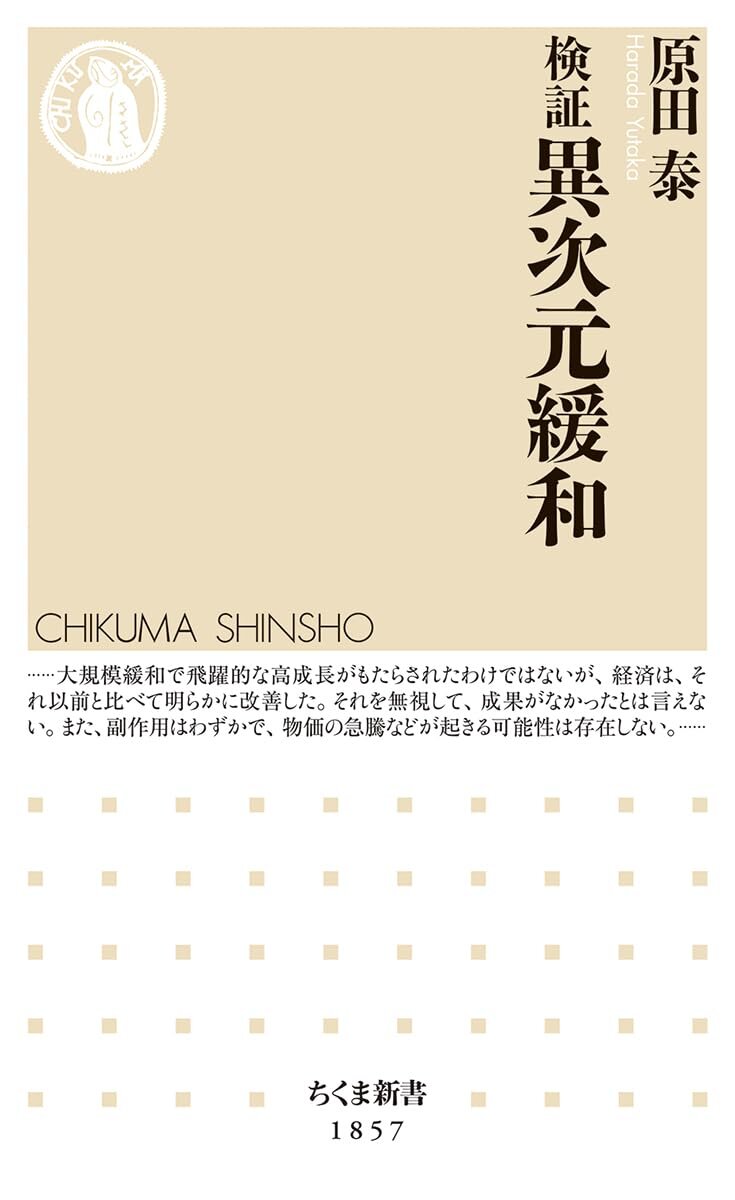
――本書執筆の経緯をうかがえますか。
私は2015年3月から20年3月まで5年間、日本銀行政策委員会審議委員を務め、その時々の日本銀行の考え、私の考え、多くの方々との議論の記録を『デフレと闘う─日銀審議委員、苦闘と試行錯誤の5年間』(中央公論新社、21年)にまとめました。在任当時も退任後も異次元緩和についてさまざまな意見・批判があり、それに対してコメント論文を書いていました。前著から少し時間も経ちましたし、それを一冊にまとめたいと思っていました。
例えば、デフレの人口理論。人口減少でモノやサービスの需要が落ち、デフレをもたらすというのですが、人口減少は供給減の要因でもあります。需要も供給も減るのですから、インフレになるのかデフレになるのかわかりません。他にも、異次元緩和は生産性の低いゾンビ企業を存続させて低成長となる、政府が資金調達しやすくなり財政規律が低下する......こうした奇妙な議論のどこが誤っているか、客観的なデータに基づいて論じています。
書き溜めたコメント論文はありましたが、短いエッセイの集積ではなく、体系的なものにしたいと考えました。そこで第2章は「金融政策とは何をするものか─目的と手段と経路」と題し、金融論の基本的な考え方を教科書的に説明し、そのなかに当時の日銀が直面した課題、私が考えたことといったさまざまな事例を挟み込むように構成しました。統一性を持たせるように記述するのはなかなか難しく、執筆にあたって苦心した点です。
――異次元緩和について、日銀も昨年12月の「多角的レビュー」で「プラスの影響をもたらした」と結論づけています。なぜ批判が根強いのでしょうか。
プラスの効果があったという点は、石破総理の豹変ぶりが最もよく示していると思います。「党内野党」時代には反安倍ということで異次元緩和にも反対していましたが、いざ自分が総理になってみれば拙速な利上げを否定することになった。現実を見て柔軟に意見を変えたのでしょう。すべての人々に現実を見ていただきたいですね。
振り返ってみると、16年1月にマイナス金利政策を導入してから批判が強まりました。「金利ゼロで不十分ならマイナスにすればよいだろう、欧州中央銀行(ECB)はじめ欧州でも実際に導入しているのだから」と、私はエコノミストとして単純に考えたのですが、世の中へのインパクトが強すぎた。テレビでは、預金金利がマイナスになると誤解されて、家庭用金庫が売れているなどと面白おかしく扱われてしまいました。国民世論を驚かせてしまったために、低金利政策に反発していた銀行も嵩(かさ)に懸かって批判するようになりました。政策は理屈だけではダメで、社会的な受容性も考えなければならなかったと反省しています。
――実務経験者ならではの貴重なお話です。ところで、22年4月以降は消費者物価上昇率が2%を超えていますが、政府はいまだデフレ脱却を宣言していません。それはなぜでしょうか。
近年の物価上昇は、エネルギー価格や食料価格の上昇といった供給面の要因が大きいです。一方、景気が拡大して需要が高まり、生産拡大と賃金上昇によって結果的に物価が上がるというメカニズムが考えられます。供給面の要因が落ち着いたときに、本当に需要面から物価が上がっているか、まだわからないということです。
実際、エコノミストの物価予想でも、来年には2%を割ると見る人が多いようです。エネルギー価格は落ち着いてきましたし、コメは消費者物価に対するウエイトも小さいですから。
今後はトランプ関税の影響も考えられます。日本の海外からの需要が減るわけで、企業は価格を下げるか生産を縮小する。つまり、利益が下がり、雇用が減り、賃金は上がらず、賃金×雇用の総賃金も減る。当然デフレ圧力になる。政府としては、いったん脱却宣言を出したのに、そうではなかったというわけにはいきません。長期的に自分の手を縛るようなことは言わないほうがよいということでしょう。
(『中央公論』2025年8月号より)
名古屋商科大学ビジネススクール教授。1950年生まれ。東京大学農学部卒業。学習院大学博士(経済学)。日本銀行政策委員会審議委員、早稲田大学教授などを歴任。『ベーシック・インカム』『デフレと闘う』など著書多数。