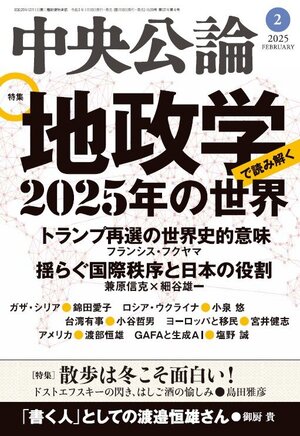髙山裕二 「独裁者」が訴えた代議制民主主義に不可欠の条件とは【著者に聞く】
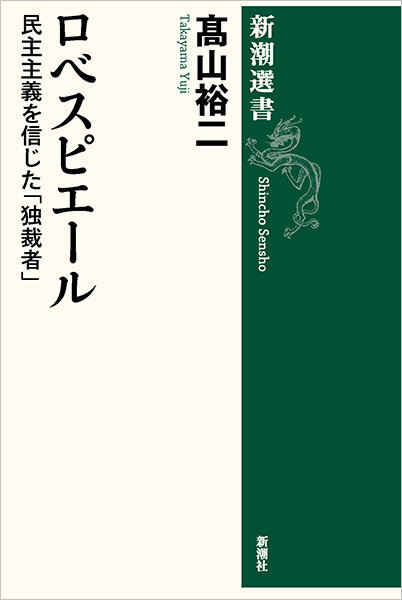
――フランス革命期、「恐怖政治」の担い手として知られた悪名高い人物の思想的側面に光を当てる評伝です。
当初は、ロベスピエールと宗教との関わりを中心とする本を書く予定でした。しかし彼の全集を読み進めるうちに、政治思想の面から見て面白い論点が浮かび上がってきました。彼の生涯を追うことで、その思想や理念を描き出そうとしたのが本書です。
もともとロベスピエールの思想はルソーの影響を色濃く受けており、人民主権を重視します。ただ、政治は人民の一致した意思、つまり「一般意思」に基づいて行われなければならない、というところまではルソーと同じなのですが、ロベスピエールは代表者の役割を強調するのです。彼は代議制を支持しており、人民が政治に直接参加する直接民主制の考え方を取りません。そこでキーワードとなるのが「透明性」という概念です。
透明性とは、代表者と人民、あるいは治者と被治者が互いに相手の考えがよく見え、意思が一致している状態を指します。彼はそれを理想の共和国、あるべき民主主義の形だと考えました。
人民一般の利益を追求する代表者(議員)に必要とされるのが、自分を含めた個別の利害関係にとらわれない「美徳」です。ロベスピエール自身、「清廉の人」と呼ばれていました。
――そうした美徳は現代でも政治家に求められる要素ですが、そこからなぜ恐怖政治に至ったのでしょうか。
代表者には美徳が必要だという論理を突き詰めれば、一部の人々の利益や権益を守る政治家は美徳を持っていない、すなわち腐敗していることになりますし、批判すべき対象とみなされます。政治の場でのロベスピエール流の美徳の要求は、容易に排除の論理へと転化する面はあると思います。
ただ、一般にはロベスピエールが独裁者となって政敵をどんどん処刑していったイメージが強いのですが、それは実態と異なっています。フランス革命での恐怖政治の主体となったのは、公安委員会という治安維持権限を握る執行機関です。ロベスピエールは公安委員会の主要メンバーではありますが、あくまでそのうちの一人です。
恐怖政治期に多数の人々が「共和国の敵」のレッテルを貼られて断頭台の露と消えたのは、ロベスピエールの美徳の論理が暴走した結果というよりも、メディアの発達に伴って陰謀論が拡散したことの方が要因として大きいでしょう。次々と内部に「敵」を見いだしていく陰謀論を、民衆だけでなく政治家たちまでが信じてしまったことが恐怖政治の原動力だと思います。もちろん、ロベスピエールが恐怖政治の流れに加担したのは事実ですが、彼をクーデターで失脚させた側が、独裁者の汚名を着せることで彼一人に全ての罪を押しつけた面は否めません。
そうした恐怖政治のメカニズムと、ロベスピエールの思想自体は区別する必要があるのではないか。彼が抱いていた理想や政治理念を通して、今日の民主主義の危機と呼ばれるような問題を検討する上でのヒントが得られるのではないかと考えました。
――ロベスピエールの思想の現代的意義とは。
いくら人民主権といっても、現実には政治を担う代表者的な存在が必要です。しかし、社会のエリートである代表者たちが、あまりにも公共の利益や国民一般の要求から離れて利己的、独善的になってしまった場合、必ず民衆から反発が起きます。現にいま、代議制への不信感、つまり既存の政党や議員は自分たちを代表していないという民衆の不満を受けて、各国でポピュリスト的な政治家が台頭しています。
その意味で、代表者には美徳が必要だというロベスピエールの主張は、いまでも否定し去ることはできないでしょう。現代において美徳などと説くのは時代錯誤かもしれませんが、かといってそうした美徳が全くなくなってしまえば、そもそも代議制民主主義は成り立たなくなるのではないか。ロベスピエールの思想と行動から、われわれが学べることは多いと思います。
(『中央公論』2025年2月号より)
1979年岐阜県生まれ。明治大学准教授。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了。博士(政治学)。専門は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(サントリー学芸賞)、『憲法からよむ政治思想史』、共著に『社会統合と宗教的なもの』などがある。