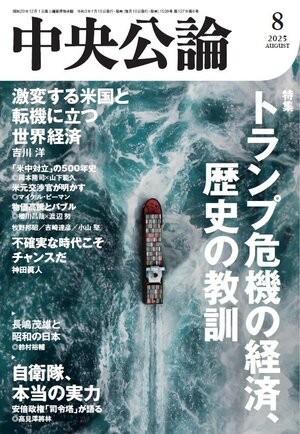『〈ていねいな暮らし〉の系譜─花森安治とあこがれの社会史』佐藤八寿子著 評者:竹内洋【新刊この一冊】
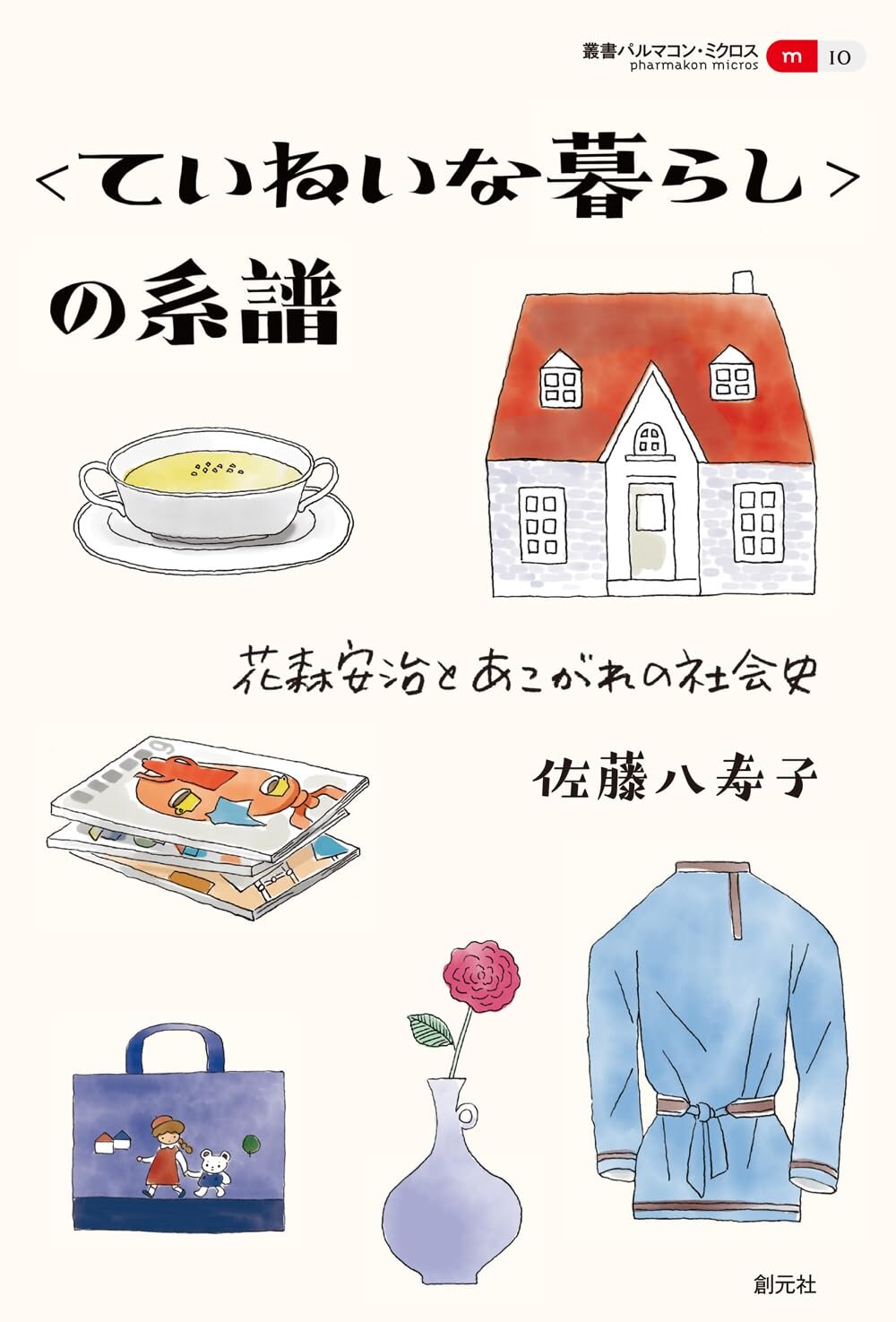
評者:竹内洋(京都大学名誉教授)
4月からNHKドラマ10「しあわせは食べて寝て待て」を視聴していた。膠原(こうげん)病に悩む女性が薬膳料理とやさしい人間関係の中で生きる術をつかんでいく。番組が終わる頃、本書が届いた。評者がこのドラマに引き付けられたのは、「ていねいな暮らし」への憧れからかもしれない。
1990年代後半から暮らし系雑誌がふえる。「ていねいな暮らし」とは、出汁(だし)は前夜から昆布を水につけて取るような、暮らしの中の小事にてま・ひまをかけ、大切に味わうことである。コロナ禍でのステイホームを追い風に、いまや憧れのライフスタイルとなった。
しかし憧れは、転じてオブセッション(強迫観念)にもなる。余裕のある意識高い系のスタイルとしてやっかみや反撥も引き寄せる。本書は、元祖「ていねいな暮らし」雑誌である『暮(くら)しの手帖』と創刊者花森安治(やすじ)(1911〜78)を解き口に、衣食住にわたる「ていねいな暮らし」方とその来歴をあざやかに描出していく。
『暮しの手帖』は山の手雑誌とされるが、著者はそこに伏在する覇権闘争をあぶり出す。『暮しの手帖』は山の手知識人の逆襲の橋頭堡(きょうとうほ)だった。そう言うのである。そもそも戦後は、本誌『中央公論』を含めた総合雑誌が、一時的な興隆はあったものの、戦前の黄金時代に比べれば低迷した。下町(育ち)知識人の台頭によって、山の手(育ち)知識人が論壇から後退させられていた。『暮しの手帖』は、戦後メディアにおける「世界」や「思想」系テーマの衰退と「暮らし」系テーマの興隆を象徴する雑誌でもあった。
この知見を片手に、著者は「ていねいな暮らし」の原型をもとめて花森が住んでいた大田区久が原(くがはら)界隈から山の手を歩き、思考を紡ぐ。山の手文化が和洋折衷だったことに着目する。そうだからこそ、てま・ひまをかける必要があった。経済的に無理をしても女中をおいた所以(ゆえん)、と言う。山の手生活とは実のところは「つつましい」教養家庭というべきもので、下町とはちがった形だが地元愛も強かったことも知らされる。「ていねいな暮らし」が山の手文化を原型とするというのはそういうことだったのだ。たしかに、向田邦子の小説に出てくる新中間層家庭は贅沢や華美から遠く、質素でつつましい。
圧巻は、「ていねいな暮らし」という静かなライフスタイルに仕掛けられる思想戦と、著者の応戦である。
小さないとなみを肯定する「ていねいな暮らし」は、SDGs(持続可能な開発目標)とともに、大状況(決定論)派から、小状況主義として攻撃の的になりやすい。現実の危機から目をそらす免罪符であると。しかしSDGsが新しい制度を支える新しい宗教(理想)なのに対し、「ていねいな暮らし」のほうは、理想をめざしても、多様性を包括するしなやかさを本領とし、融通無碍(ゆうずうむげ)で適当なところもある。コロナ禍で台頭した「新しい生活様式」派をピューリタニズムとすれば、「ていねいな暮らし」はカトリシズム(普遍主義)と、快刀乱麻を断つかのような見立てに唸る。
「SDGsへの小さな貢献や〈ていねいな暮らし〉への無垢なあこがれは、強制も禁止もされたくない」という著者の願いと祈りが心を打ってやまない。向田邦子さんに読んでほしかった。江藤淳さんにも。
(『中央公論』2025年8月号より)
◆佐藤八寿子〔さとうやすこ〕
1959年東京都生まれ。上智大学卒業後、ミュンヘン国際青少年図書館勤務などを経て、京都大学大学院教育学研究科博士後期課程学修認定退学。2011年より文化サロンKollegium Kyoto主宰。著書に『ミッション・スクール』、共訳書に『ナショナリズムとセクシュアリティ』などがある。
【評者】
◆竹内洋〔たけうちよう〕
1942年東京生まれ。佐渡島で育つ。京都大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学。専門は教育社会学。京都大学教授、関西大学教授を歴任。『教養主義の没落』など著書多数。