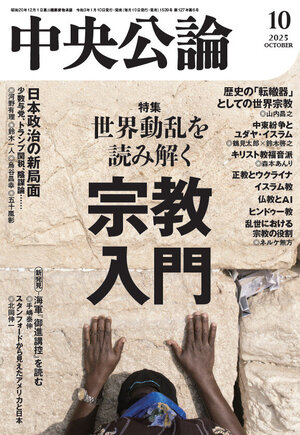『国宝』からはじめる歌舞伎入門
女形
喜久雄は少年時代に女形の卓抜した資質を見出されて半二郎の内弟子となる。半二郎自身も女形を演じる役者であり、俊介もまた新進気鋭の女形として将来を約束された劇界のプリンス。
歌舞伎では原則として女性の役をすべて男性の役者が演じる。西洋風にいえばオールメールの演劇である。しかし17世紀初めに生まれた歌舞伎は、もともと男女混合で演じられていた。
一般に歌舞伎の始祖として「出雲のお国」と呼ばれる人物が男装の女性だったことが象徴するように、初期の歌舞伎では女性が男性を、男性が女性を演じることが行われ、演じ手はむしろ女性の方が主体となっていた。彼女たちの多くは遊女でもあったが、風紀を乱すという理由で幕府によって女性の出演が禁じられ、やむなくすべての役を男性が演じることになる。当初は元服前の少年である「若衆(わかしゅ)」が演者となったが、彼らもまた身を売る少年たちであった。また禁に反して女性の出演も相次いだため風紀維持の目的は達せられず、次いで若衆の出演も禁止。成年男性である「野郎」が歌舞伎を担うこととなった。ここに「女形」という芸が確立することとなる。
以後、女形は「男性の身体を使って女性を表現する」という困難を乗り越えるために、様々な演劇的技巧を開発していく。高い身長やがっちりした肩幅、武骨な手指をできるだけ小さく見せて、大きな体を華奢で可憐な女性であるかのように思わせる。独自の発声とせりふ回しによって、男性の声帯でもまるで女性が喋っているかのように感じさせる。指先や視線の動きから衣裳の布が形作る曲線まで、とろけるように柔らかく優美な所作。内股にするため、膝の間に挟んだ紙を落とさずに歩く稽古をしたという話はよく知られている。
イギリス・エリザベス朝演劇の少年俳優、中国の京劇の旦など、世界の演劇に男性が女性を演じた例はあるが、これだけの複雑で高度な演技術を開発し、それが現代にも行われている演劇は非常に珍しい。
しかしそれらの技巧はすべて、人間の身体の構造からいって相当の無理を強いられる。膝は内側に折り縮め、腰をひねり、左右の肩甲骨を限界まで寄せて常に撫で肩を作っていなければならない。つまり女形の芸は、人間としての自然に逆らう、極めて人工的な形や動きを必要とする技巧であって、それが目指すものは決して本物の女性をリアルにコピーしようとする物真似芸ではない。あくまでも幻想としての女性像の体現である。それは観客が「いかにも女性らしい」と感じるイメージを抽出し極端に拡大してこしらえた作り物であって、現実にそんな女性は存在しない。
映画では失意の旅回りを続ける喜久雄が客にからまれて「にせものじゃねえか」と罵倒される場面があるが、女形の魅力はまさにニセモノ、マガイモノならではのいかがわしさにこそある。男性でありながら女性に変身したい、男性の肉体から飛び立ちたいという意志が、身体という絶対的な足枷とのせめぎ合いの中で屈折し内攻することによって、女形は独特の危うい美しさを生み出す。東洲斎写楽が描いた女形のようなグロテスクで異形のものが、舞台の上ではどう見ても美しい女性としか思えないところに女形の不思議があり、女形とは歌舞伎の舞台という限られた虚構の空間の中でしか生きていられない特殊な生き物なのである。
映画の中でそれを象徴するのが、喜久雄と俊介に大きな影響を与える小野川万菊(田中泯)。田中泯はいかにも芸に殉じる老女形のただならぬ気配を感じさせる名演で、圧倒的な存在感を放っている。
なお歌舞伎の舞台に女性が出られないのは前近代的だと批判されることがあるが、もともと神事だった大相撲の土俵に女性が立てないのとは違って、歌舞伎には別に伝統的な決まりごとがあるわけではない。江戸時代の御狂言師(おきょうげんし)、明治時代の女役者のように歌舞伎を専門に演じる女性もいたし、現代でも一時期東宝が主催した東宝歌舞伎をはじめ、歌舞伎役者と女優との共演はしばしば行われてきた。
ただ、リアリズムに背を向けて作り上げられた様式の極致のような女形の芸と、生身の女性である女優の芸とは当然性質が異なる。女形の芸はいわば男性の身体というOSの上に組み上げられた精密なプログラムであって、女性の身体ではうまく作動しない仕組みになっている。そして歌舞伎の舞台上にあるすべてのもののバランスは、女形というプログラムを前提として設計されている。歌舞伎が男性のみで演じられているのは、そもそも構造的に女性が演じない演劇としてスタイルが構築・完成されてしまったことに理由がある。
(『中央公論』10月号では、この後も、化粧、家と門閥、襲名、舞踊というポイントに分けて、歌舞伎をより味わうための見どころについて論じている。)
1970年徳島県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得満期退学。博士(文学)。専門は、幕末から明治期の歌舞伎を中心とする日本芸能史・文化史。著書に『明治キワモノ歌舞伎五代目尾上菊五郎の時代』(サントリー学芸賞)、『明治の歌舞伎と出版メディア』『ちゃぶ台返しの歌舞伎入門』などがある。