『認知戦─悪意のSNS戦略』イタイ・ヨナト著/奥山真司訳 評者:梶原麻衣子【新刊この一冊】
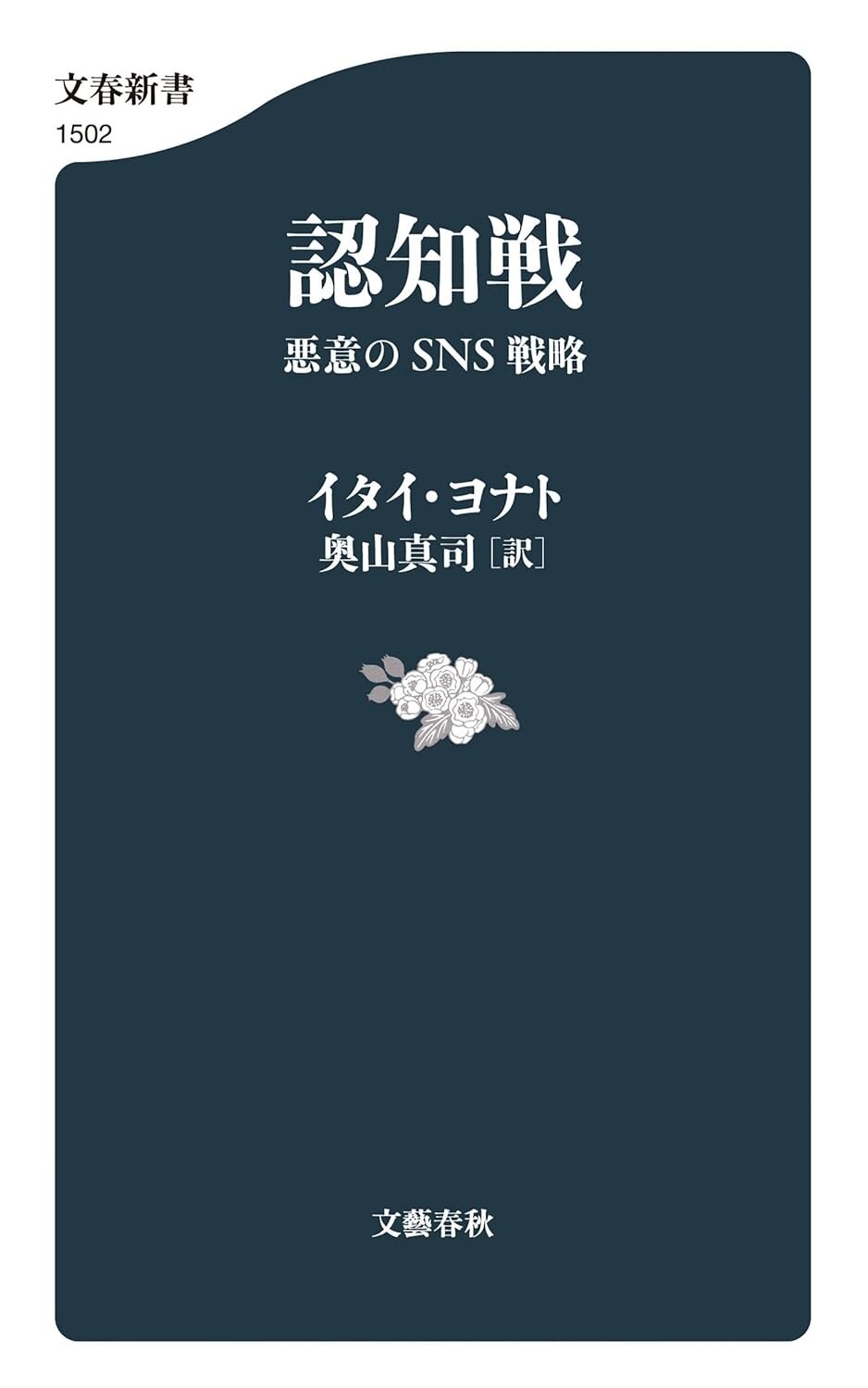
評者:梶原麻衣子(編集者、ライター)
巧妙さを増す中国やロシアの情報工作は、ネットによって国境を越え、さらには知識やリテラシーの壁をも乗り越えて、我々の認知、つまり脳を狙って攻撃を仕掛けてくる。誰もが気づかないうちに、中露の望むナラティブ(物語)を信じ込み、社会へ拡散している可能性がある。
認知戦と呼ばれるこうした現状をコンパクトにまとめているのが本書だ。著者のヨナト氏は認知戦を仕掛ける側としてイスラエル軍で働いていたプロ中のプロ。現在はその経験を生かし、認知戦の分析や調査、防衛策を講じる自身の会社を経営する。そのため本書でも、実践的な現状分析と対策を示しているのだ。
例えば福島原発のALPS処理水の問題。中露は日本を貶めるために「汚染水」という名称を使い、処理水放出時にはことさら危険性と不安を煽ってきた。幸い、外務省が海外向けにも安全性の宣伝を行ったことで被害は拡大しなかったが、著者は、日本の評判を守るための中露への反論だけでは不十分であり、中露こそ汚染されたままの水を海に放出していると反撃すべきだったと手厳しい。
しかも、日本国内の一部メディアはいまだに「汚染水」との名称を使っている。プロパガンダに使われていることに気づかないまま、「自分は正しい、正義に基づく発信を続けている」と信じているような人々を、ヨナト氏は認知戦を仕掛ける側にとっての「役に立つ馬鹿(useful idiot)」と呼ぶ。
認知戦の恐ろしさはこの点にある。いつの間にか作られたナラティブや誤った情報、認識が頭に刷り込まれ、正しいと思い込んで他者を批判・攻撃するようになる。それによって社会に相互不信の種をまき、社会を不安定化・弱体化させ、国際的に日本を孤立させる。中露の狙いはそこにあるのだ。
もう一つ、本書から得られる重大な教訓がある。「認知戦の罠」だ。これは筆者(梶原)の造語だが、認知戦の存在を知ると、自分にとって都合の悪い情報や状況に対して「人々は他国の認知戦に影響を受けているのではないか」と認識してしまう現象が起きるのだ。
ヨナト氏は祖国であるイスラエルが、敵対するハマスやイランが展開する認知戦の影響で国際的な共感を得られていないと述べている。つまりハマスやイランの認知戦に、国際世論が騙されているととらえているのだ。
確かにイランやハマスはあらゆる宣伝工作を展開していよう。だが、パレスチナへ攻撃を続けるイスラエルへの国際的な同情が低調なのは、そうした認知戦の影響よりも「現実(事実)」としてイスラエルの振る舞いに疑問を持つ人が多いからではないか。
戦時下の国に暮らし、本書の編集中も志願兵としてガザの戦地に赴いていたというヨナト氏に対して、あまりに厳しい物言いに聞こえるかもしれない。ましてや氏は認知戦のプロ中のプロだ。だが、知識があるからこそこうした「認知戦の罠」に陥ることもあるのだと指摘したい。
認知戦とは、かくも人々の脳(認知)と心(感情)をかき乱すものなのだ。結果として生じる被害も甚大である。その意味でまさに認知戦は戦争の一類型であり、本書が示す教訓は貴重である。
(『中央公論』2025年11月号より)
◆イタイ・ヨナト〔Itai Yonat〕
1968年生まれ。OSINT(公開情報の収集・分析・活用手法)インテリジェンス企業「インターセプト9500」創業者兼CEO。イスラエル軍の諜報部員として様々な作戦に従事。現在は各国政府のアドバイザーを務める。
【評者】
◆梶原麻衣子〔かじわらまいこ〕
1980年埼玉県生まれ。中央大学文学部史学科東洋史学専攻卒業。IT企業勤務後、月刊『WiLL』、月刊『Hanada』編集部を経てフリーに。著書に『「〝右翼〟雑誌」の舞台裏』。













