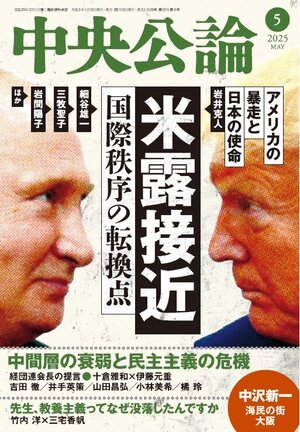『ネオリベラリズム概念の系譜 1834─2022』下村晃平著 評者:稲葉振一郎【新刊この一冊】
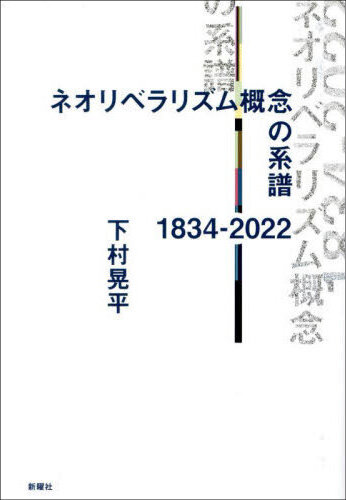
評者:稲葉振一郎(明治学院大学教授)
「ネオリベラリズム(新自由主義)」という言葉がある時期以降、内容空虚なプラスチック・ワードの典型として濫用されていることには以前から憤懣やるかたないものがあった。とりわけ日本では、さらに醜悪な「ネオリベ」という略称まで流布するようになったことに腹を立て、私も『「新自由主義」の妖怪』(亜紀書房、2018年)を書き上げた。拙著の主題は人々が「新自由主義」の語で指し示そうとしている現象(思想傾向だの政策パッケージだの、あるいは資本主義の新局面だの)を、「新自由主義」という語に惑わされずに、できるだけ丁寧に腑分けして見ていこう、というものだった。つまり言葉や思想にではなく、社会経済的な現実、実態の方に主題があったと言える。
それに対し、新進の社会学者が世に問うた本書の主題は、「ネオリベラリズム(新自由主義)」という言葉そのものの使われ方を解明することにある。「ネオリベラリズム」という言葉は多義的であいまいである。特に批判的、否定的な意味で用いられる場合には、具体的にどんな対象を指し示しているのかさえ定かではない体たらくであって、社会経済的な現実を理解しようとするときには、むしろ使うべきではない。にもかかわらずこの言葉が頻繁に使われてしまっているということ自体、別の水準での社会的現実に他ならない。本書の主題はそちらの方にあり、学問的には「社会思想史学」「知識社会学」と呼ばれるものだ。仮に根も葉もない嘘やでたらめでも、それが流布しているならば、そのこと自体が社会科学的な関心の主題になるし、またそうした嘘やでたらめを信じた人々の行動が社会を現実に(良い悪いは別として)変えてしまうこともあるとなれば、案外実践的な意味もある。
本書の前半は、20世紀半ばに特定の学者・思想家集団によって作られ、それなりにまとまりのある思想体系(とはいえそこには国ごとの多様性があり、後世に強い影響を与えた英米系以外の潮流は中途で衰弱し忘れられたのだが)に与えられた「ネオリベラリズム」という名前が、当事者たちによる自称としては捨てられた経緯を描く。続く後半では、20世紀末に彼らの思想が脚光を浴び、現実の政策に大きく影響するようになってから、主としてその批判者による他称として用いられるようになった経緯も描き出していて興味深い。
このように見ていくと、「ネオリベラリズム」が得手勝手に濫用されるプラスチック・ワードと化したのはもちろん本書の後半で描かれた過程においてだが、そうなってしまったことへの責めをもっぱら「ネオリベラリズム」批判者たちの知的怠惰に帰すことも公平とは言えない。現在の議論の噛みあわなさには(かつての?)新自由主義者の方にも責任があるのかもしれない。もちろん著者の関心は主として、言葉の使われ方の歴史を禁欲的に描き出すことにあって、あれこれお説教をすることにはないが、そのような主張を読みとることもできなくはない。
著者の示唆に従うなら、「ネオリベラリズム」の代表選手たるハイエクやフリードマンといった経済学者たちが、元来「自由主義の刷新」を目指していたはずなのに、いつしか古典的自由主義と自分たちとの連続性、正統性を強調するようになったことと、「新自由主義者」を名乗らなくなったことの間には何らかの関係がありそうだ。
(『中央公論』2025年5月号より)
◆下村晃平〔しもむらこうへい〕
立命館大学衣笠総合研究機構専門研究員。1990年京都府生まれ。立命館大学大学院社会学研究科博士課程後期課程修了。博士(社会学)。
【評者】
◆稲葉振一郎〔いなばしんいちろう〕
1963年東京都生まれ。一橋大学社会学部卒業。東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。著書に『ナウシカ解読』『社会学入門』『市民社会論の再生』など。