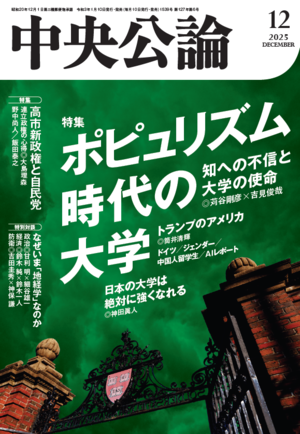「連立政権合意書」を読み解く――求められる経済政策の新時代

総裁就任から半月以上を経て、10月21日に高市早苗内閣が発足した。我が国初の女性総理の誕生である。一方で、公明党の連立離脱とそれにともなう与野党総出の政局を経て、電撃的に日本維新の会との閣外協力に至った混迷は、高市政権の運営が容易なものではないことを示している。
26年間続いた自公連立の解消、維新との連携、政策本位を掲げる国民民主党との協議は政治・政策の在り方を大きく変えることになるだろう。こと近年の国政選挙で常に有権者最大の関心事となっている経済政策は大きく動き始める。この機会を日本経済再生の出発点としなければならない。
多党制時代の政策実現
自民・維新の「連立政権合意書」(10月20日)では、実現に向けて取り組む政策として12の項目が列挙されている。その内容は経済政策にとどまらず安全保障、皇統、さらには現下の焦点である議員定数削減にまで及ぶが、本稿では経済政策を中心に概観しよう。
合意政策の第一には「一、経済財政関連施策」として、ガソリン旧暫定税率の廃止や物価対策などが挙げられている。政府効率化局による高額補助金の点検に言及している点は、補助金行政とそれにまつわる利権構造にメスを入れてきた維新ならではの提案であろう。
提示される論点は、自民党総裁選での高市氏の主張と重なる部分が多い。給付付き税額控除や「六、エネルギー政策」における原発再稼働・次世代革新炉の開発推進に加え、国土政策としてのメガソーラー規制は国民民主の協力を得やすい論点でもあり、今後の大きな進展が期待される。
「二、社会保障政策」の詳細さも特徴的だ。7月の参院選で維新はマニフェスト紙面のほとんどを社会保険料問題に割いたが、党勢拡大にはつながらなかった。それでもなお喫緊の課題として改革の旗を降ろすことのなかった維新の信念は高く評価されよう。多くの党が社会保障改革を掲げるが、維新の提言は具体的で、それゆえに反発を生みやすいものも多い。従来の政権枠組みでは実現困難だった改革をどこまで進めていくことが出来るか、新政権の実行力が試される。
一方で、連立協議のなかでやや唐突感のある「絶対条件」として提示されたのが議員定数の削減である。同党結党以来の主張ではあるが、近年の国政選挙では注目されてこなかった。このタイミングで定数問題を交渉の中心課題とした意図は現時点ではわからないが、選挙制度こそが中長期的には政治・政策の方向を決定する。選挙制度、選挙区の大小、比例制度の有無によって当選に資する公約や政策実践は異なるからだ。首班指名のための条件としての定数削減を自民党は大筋で受け容れた模様だ。(10月20日現在)。
当面の政策は、自民党と維新、そして国民民主との協調と緊張関係のなかで決定されていくこととなろう。綱渡りの政権運営だからこそ、正確な現状把握と論理的な政策立案が必要とされる。
(『中央公論』12月号では、景気と物価、社会保障、選挙制度についての政策方針を提言している。)
1975年東京都生まれ。東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。財務省財務総合政策研究所上席客員研究員、総務省自治体戦略2040構想研究会委員などを歴任。専門はマクロ経済学、経済政策。単著に『財政・金融政策の転換点』、共編著に『高圧経済とは何か』など。