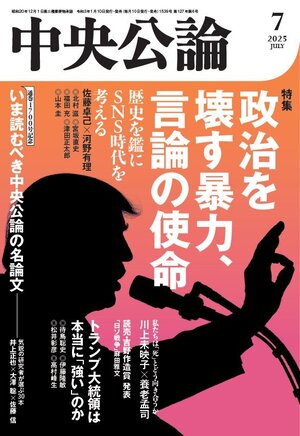水野太貴「「女ことば」の背後にあるもの――社会言語学者・中村桃子さんに聞く」
どう生まれ、使われたのか
女ことばというのは、よくよく観察してみると謎だらけだ。
「あら、雨ですわ」「まあ、ぶざまなこと」......コテコテの女ことばを挙げてみた。僕たちはこの発言を読めば、女性が話しているのだとわかる。しかし少し立ち止まって考えてみてほしい。現実でこんなことば遣いをする人を見たことがあるだろうか。ここまであからさまでなくてもいい。「~だわ」「~わよ」といった終助詞でさえ、僕は同世代の友人が使っているのを見たことがない。つかもうと手を伸ばしたら、するりと指の間をすり抜けていくような錯覚。あれ、僕が知っていた女ことばって、何だったんだろう? そして、なぜ理解できるのだろう?
中村さんは、女ことばがいつ、どのように生まれたのかを調べ上げた。その成果は一連の著作に詳しいが、そのエッセンスを教えてもらった。
「ファンタジー小説の『ハリー・ポッター』シリーズの登場人物・ハーマイオニーのセリフがあります。
『まあ、あんまりうまくいかなかったわね。私も練習のつもりで簡単な呪文を試してみたことがあるけど、みんなうまくいったわ』
これはハーマイオニーが初めて登場するシーンのセリフですが、典型的な女ことばで訳されていることがわかります。このように、現代の私たちが実際に女ことばを見聞きするのは映画やドラマ、マンガ、小説など、フィクションの世界においてであり、それが女性と結びついて理解されていると考えられます」
つまり、現実世界でのことば遣いではなくフィクションによって、ある形式と特定の属性の結びつきが生み出されたということだ。これは女ことばに限った話ではなく、例えば「はて、雨じゃ」と実際に話す人を見たことがなくても、こうしたことば遣いをするのは老年男性だと僕たちは知っている。このような特定の人物像を思い起こさせることばを「役割語」といい、日本語には役割語が豊富に存在する。
(『中央公論』7月号では、「女ことば」がどのような歴史を辿ってきたのか。また嫌われがちな、「ヤバいっす」などの「ス体」、「させていただく」の意義についても、詳しく論じている。)
1995年愛知県生まれ。名古屋大学文学部卒業。専攻は言語学。出版社で編集者として勤務するかたわら、YouTube、Podcastチャンネル「ゆる言語学ラジオ」で話し手を務める。著書に『言語オタクが友だちに700日間語り続けて引きずり込んだ言語沼』などがある。
◆中村桃子〔なかむらももこ〕
1955年東京都生まれ。上智大学大学院修了。『「女ことば」はつくられる』で第27回(2007年度)山川菊栄賞受賞。専門は言語とジェンダー。『「自分らしさ」と日本語』『ことばが変われば社会が変わる』ほか著書多数。