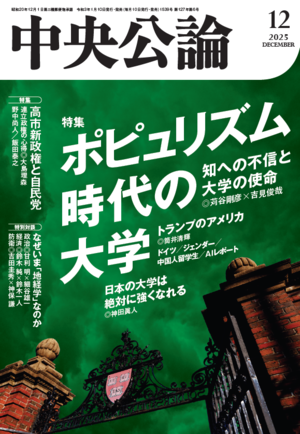実在しない参考文献、知らぬ間の「盗作」......学生の生成AI利用にどう向き合うべきか
教員の「目の奥の知識」が不正を見抜く
提出されたレポートで生成AIが使われているかどうかは、チェックツールを使って調べることができる。Turnitinやコピペルナーといった、学生のレポートでネットなどからの盗作がないかを調べる「剽窃防止ツール」が、現在では生成AIの使用可能性まで判断してくれるようになっている。もっともそのチェックは完璧ではないし、可能性を示すだけで、最終的な使用の有無までは断言することができない。
しかし、レポートを受け取った側としては、そのレポート作成で生成AIを使用しているかどうかは、意外と分かってしまうものである。もちろん、勘違いや思い過ごしもあると思うが、大きく間違えることはないだろう。参考文献については、存在しない論文・本ではないかという点は即座に勘が働くし、それが外れることはほぼない。このことを以下のようにSNSに投稿したところ、大きな反響があった。
【大学教員がAI作成ウソ参考文献を見抜くポイント】
5位 そんな論文雑誌はなかったような...
4位 その人とその人は共著しないだろ...(夢の共演)
3位 著者名知らないな...
2位 その人の著作は全部知っているからウソだ
1位 この分野の本は全部読んでいるからウソだ
この順位には、とくに根拠はない。面白おかしくするために順番を付けただけである。しかしそれぞれの内容は、本当に「架空文献」に気づくポイントを示している。まず大前提として、教員が行っている授業は、自分が専門としている研究分野と関連が強い。専門としているならば、その分野の学術論文雑誌名はほぼ知っているものなのだ。これは、自分が読むだけでなく、授業準備や学生指導も含む、多様な機会で度々触れるからである。だから、ちょっとでも違和感がある雑誌名だと、そんな雑誌あったかな......と思うのだ(第5位)。
同様に、自分の研究分野に近い研究者の論文はだいたい目を通しているし、学会でも名前を見るのでおおかた知っている。だから、既知の研究者以外の人がその分野でクリティカルな論文を書いていたら、すぐに気がつく、というか、気になって原典を検索してしまう(そして架空文献に気づく)のが研究者の性というものである(第3位)。
だから、あの著者とこの著者とが一緒にこのテーマで研究することはない、ということにもすぐに気づく(第4位)。本当だったらまさに「夢の共演」なので、ワクワクしながら調べてみて、架空文献であることに逆にガッカリする、なんてことも起きる。
2位と1位は、さすがにおおげさだろう、と思われるかもしれない。しかし、そうとも言い切れないのである。先に書いたように、著名な研究者であるほどその人の学術的な著作は把握している。ときには、ある研究者を勝手にライバル視することもある。そんな相手の著作は、本文まで読んだことはなくとも、だいたいの論文は一覧として理解しているものだ。さらには共同研究などしていたら、お互いの業績リストを見ることも多いし、行っている研究については頻繁に情報交換する。そうしたことから、2位に書いたように、ある特定の(分野の近しい)研究者の著作をだいたい把握している、というのはわりとあることなのだ。
では、1位の「この分野の本は全部読んでいる」はどうなのか。これも本当にありうる。簡単な話で、論文や本を書くときには、そのテーマに関連した先行研究をくまなく調べるからだ。そこでは、読んだけれども参考文献として引用することはなかった、というものも大量に出てくる。挙げた参考文献の10倍以上の本・論文は当たり前に、(文系の)研究者は読んでいるものである。
また、書店などで自分の研究分野の新刊が出ていたら、とりあえず購入する。それが無理なら、パラパラと立ち読みするか、少なくとも著者名とタイトルは覚えておく(そして後で図書館で借りたりする)。さらに所属学会の雑誌に掲載された、自分のテーマに関係がある論文はすべて目を通す。このように、全部をきちんと読んではいないにしても、特定の分野の出版物についてだいたい把握しているということはありうるのだ。
こうした積み重ねが、「目の奥の知識(ビハインド・ジ・アイズ・ナレッジ)」をつくる。これは、読書研究において使われている用語である。経験豊富な読者は、それまで読んできた本の内容のみならず、社会生活のなかで得られる情報など、書籍に関する広範な経験やメタ知識の蓄積を活用することによって、「次に読む一冊」を決めている、ということを示す概念である。
ちなみに私は最近、新たに「読書」を研究対象とするようになったのだが、少し前まで中心的に研究していたNPOとボランティアについては、日本語の論文・本ならばそうした勘がすぐ働いた。それだけでなく、より周辺的な領域においても、ここまで述べてきたような学術的な生活の様々な場面での蓄積が、ウソ文献を見抜く「目の奥の知識」となっている。
(『中央公論』12月号ではこの後、生成AI時代におけるアカデミック・ライティング教育のあるべき姿について論じる。)
[参考文献]
Kim, J., Lee, S.-S., Detrick, R., Wang, J., & Li, N. (2025a). Students-Generative AI interaction patterns and its impact on academic writing. Journal of Computing in Higher Education
Kim, J., Yu, S., Detrick, R., & Li, N. (2025b). Exploring students' perspectives on Generative AI-assisted academic writing. Education and Information Technologies, 30(1), 1265-1300.
Lee, H.-P. (Hank), Sarkar, A., Tankele
vitch, L., Drosos, I., Rintel, S., Banks, R., & Wilson, N. (2025). The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects From a Survey of Knowledge Workers. Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.
Miao, F., & Holmes, W. (2023). Guidance for generative AI in education and research. Unesco Publishing.
1975年長野県生まれ。立命館大学大学院政策科学研究科博士後期課程修了。博士(政策科学)。専門社会調査士。著書に『コミュニティの幸福論』『福祉NPO・社会的企業の経済社会学』(日本NPO学会賞優秀賞)がある。