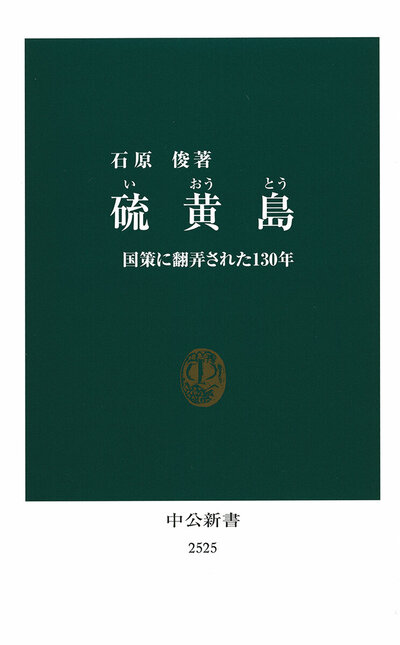今なお帰れぬ故郷――復興から取り残された硫黄島民の戦後
断ち切られた島の生活
戦前の硫黄列島は、閉鎖的・搾取的なプランテーションであるにもかかわらず、同時代の本土の小作人の状況、特に農業恐慌に苦しんだ東北地方の小作人の生活水準からは想像できないほど、「豊かな島」だった。
この「豊かな島」の生活を断ち切ったのが、アジア太平洋戦争だった。1944年に入ると、日本は開戦前の版図であった南洋群島(ミクロネシア)に本格的に攻め込まれた。この近代以後初の事態に日本軍がとった対応は、版図内にある北西太平洋のあらゆる島々を、地上戦または兵站線(後方支援ライン)の場として想定することだった。そのために各島で実施されたのが、10代半ばから50代ぐらいまでの男性を残留させて軍属として動員する一方、女性と高齢・幼年の男性は疎開させるという、冷徹な軍事政策であった。
マリアナ諸島が米軍の手に落ちると、地形が平坦で千メートル超の滑走路をもつ硫黄島は、次の主要標的となる。硫黄列島では小笠原群島(父島・母島など)とともに、右の動員/疎開政策が、他の島々に比べても徹底的に実施された。女性全員と高齢・幼年男性を合わせて、硫黄列島全体で約1100人が強制疎開の対象となった(北硫黄島は青壮年男性含む全島民が強制疎開となった)。かれらは疎開時、一人あたり風呂敷二・三包の荷物を除き、家屋・家財・畑・船舶など、ほぼ全財産の放棄を余儀なくされた。
一方、硫黄島では16歳から59歳の島民男性の多くが、疎開する家族と引き離され、軍属として徴用された。かれらは食料の調達・調理や道案内などに従事させられた。地上戦開始まで硫黄島に残留させられた島民は約100人だが、その大多数が犠牲になり、生還者は約十人にとどまった。
日本は1945年秋以後に予定されていた本土決戦を迎える前に、ソ連の参戦と米国の原爆投下によって降伏する。日本軍は北西太平洋の多数の島々において組織的な動員と疎開を実施し、硫黄島を含む複数の島々(沖縄、南洋群島、フィリピンなど)で凄惨な「住民を巻き込んだ地上戦」を展開しつつ、本土住民には同様の経験をさせない段階で敗北・解体したのだった。
なお、当時の日本帝国における法制度上の内地に限っても、南樺太と硫黄島で「住民を巻き込んだ地上戦」が行われた事実を銘記したい。現在の日本国内に限っても、沖縄戦が「住民を巻き込んだ唯一の地上戦」だとする言説は、事実に反している。
日本の降伏後、米軍は硫黄列島を小笠原群島(父島・母島など)とともに占領下に置いた。硫黄列島民は戦時強制疎開後、本土に留め置かれていたが、米国はかれらに一切帰島を認めなかった(小笠原群島民も一部を除いて帰島を許されなかった)。その間、冷戦状況の激化に伴い、硫黄島は着々と軍事拠点化されていった。同じく地上戦を経た沖縄島では、住民のいる状態で米軍基地の拡充が進められたが、面積と人口規模が小さい硫黄島は、住民を排除した状態で秘密基地化されたのである。
(『中央公論』9月号では、戦後も帰島を先延ばしされ続けた歴史や島民たちの願い、近年の動向などについて詳しく論じている。)
石原俊 著
小笠原群島の南方に位置する硫黄島。日本帝国が膨張するなか、無人島だったこの地も一九世紀末に領有され、入植・開発が進み、三〇年ほどで千人規模の人口を有するようになった。だが、一九四五年に日米両軍の凄惨な戦いの場となり、その後は米軍、続いて海上自衛隊の管理下に置かれた。冷戦終結後の今なお島民たちは、帰島できずにいる。時の国策のしわ寄せを受けた島をアジア太平洋の近現代史に位置づけ、描きだす。
1974年京都府生まれ。京都大学大学院文学研究科(社会学専修)博士後期課程修了。博士(文学)。千葉大学助教などを経て現職。専門は歴史社会学。著書に『近代日本と小笠原諸島』『〈群島〉の歴史社会学』『群島と大学』『硫黄島』『シリーズ戦争と社会』(全5巻、共編著)など。