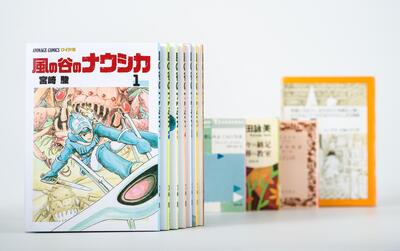鈴木涼美 権力者が「わきまえる女」を好きなのは当たり前、女性たちの戦いの核心はどこにある(斎藤美奈子『モダンガール論』を読む)
核心は、性差と階級差のせめぎ合い
歴史学者の書いた本に比べて多少の乱暴さはあるし、そもそもすでに20年以上前の本だ、と思う女性は多いのかもしれません。著者自身、2003年の文庫化の際にすでに「いま、日本をおおっているのは『退屈さ』というより、もっとはっきりした『不安』です」と、刊行時とのタイムラグによる空気の変化に言及していますが、そこからさらに長い時間をかけて、世の中の流行や女性たちの戦いの内容は随分変化してきました。
それでも、むしろ今の若者こそ改めて本作を読み返してほしいと思うのは、ひとつには、今盛り上がっている女性たちの気分を歴史的に位置付けてみるのにこんなにわかりやすく便利な本がなかなかないからです。たとえば今自分が酷い女性差別を問題視して抗議をしようとしていて、SNSで男性や時には女性からのバッシングに悩んでいるとしたら、さらっと描かれる「青鞜」や「ウーマンリブ」叩きの典型例を見れば、どれもこれも同じ手口だと呆れると同時にシラケすらするかもしれません。「過激な行動をあげつらって非難する」も、「実はカワイコちゃんだと嘲笑する」も、バッシングとして使い古されたパロディに見えます。自省的な点では、たとえば1972年の主婦論争の時に女性たちが、すでに「それが『出世の道』だったことも『貧乏人のリベンジ』だったことも忘れて」いたことを改めて発見すると、では今自分らが感じている不満はかつての女性たちにとってどんなものだったのだろうという一息ついた視点を持つことにつながります。SNSでキャッチーな言葉が飛び交う昨今、そういった視点を持つことは殊更有意義に思うのです。
もう一つ、本作が今の女性たちを救うと思う理由は、この本が男女差と階級差のせめぎ合いという今日的な課題の核心にも触れているからです。女性の不満が棚上げになったり、運動がいまいち広がらずに頓挫したりするとき、そこには往々にして階級差や貧困の問題がつきものです。それだけでなく、女性の不満が性差によるものだけでなく、階級差によるものであったということも多くあります。今、SNSの普及や時代の流れも手伝って、女性たちの不満が噴出していますが、同時に長期にわたる低い成長率とコロナ禍の経済危機までついて階級差も人々の首を締めています。今自分が感じている不満のどれだけが性差別の問題でどれだけが階級差の問題なのか、と問うことをやめてしまうと、有意味な方向に解決の手段を探しにいけないかもしれない。だからこそ、その双方がどのようにせめぎ合って今の女というものができてきたのか、という視点で本作に触れることは非常にタイムリーな話題とリンクすると思うのです。