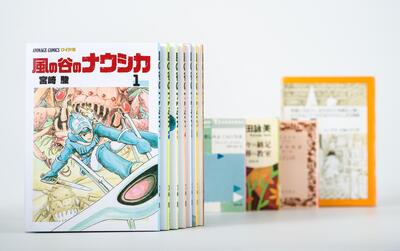鈴木涼美 シニシズムの代償を払ってなお、言葉で切り刻んだ空気の隙間から見る世界は魅力的だった(『夜になっても遊びつづけろ』を読む)
生きることの実感に繋げるために
このエッセイ集の中で、母親という存在について綴られた箇所を引用します。
「その肉親としての血の繋がりも含めて、わたしたちの生の原点であり、日常性であり保守性であり、子供からは裏切られることしかない存在なのです。それだけに彼女の力は、彼女が単に母親であるという理由だけで無限大なのですから、決定的に母親の期待を裏切る精神上の体験を通してでなくては、わたしたちは、あらゆる闘争の中で花開くヴァイオレンスの紅い花を咲かせることはできません」
それから幸福について、「青い鳥」のチルチルとミチルが、これから生まれてくる自分らの弟が、生まれてすぐ死ぬことになっていることを知ってしまった時の描写を交えてこのように書かれている箇所があります。
「『じゃあ、何のために生れてくるのさ!』とチルチルは叫ぶのだけれど、本当に、それでは何のために生れてくるのだろう? 幸福とは、そういうものだ。最初から死ぬことがわかっているのに、それでも生れてこなくてはならないもの。本当はありもしないのに、探すことを強制されたもの? それは多分観念上の所産であって、観念の生み出すあらゆる所産物が、狂気や妄想や陰惨な情熱に充ちた空中楼閣であるように、幸福という観念も、本来は狂気や迷妄に属するものなのである。だから、幸福な結婚や、御家庭の幸福や、幸福な恋人、なんてものは、本来存在しないし、存在したためしもない」
こうした文章は確かに60年代的な態度を持っていて、何でも手短に巧い!と言わせ、なおかつあたかも絶対的と思われているような善悪を大きく裏切ることなく、心を和ませ、無難に震わせる回答が好まれる大喜利ネット社会においてはそれほど重宝されない傾向もあります。若者たちは若さや幸福、あるいは母親との諸問題について、誰かの気の利いたコピーでいっときは理解した風を装っても、結局なかなか生きることの実感には繋げられないでいるわけです。圧倒的な暇と役不足の身体を抱えて過ごす若さという時間を、「謳歌」するのも、大いにフイにするのも、まるで世界の未来のためかのように生真面目に消費するのも、個人的にはアリだと思いますが、生きづらいというわかりきった事態を、巧いこと言う!と言われるためだけに言い続けるのは時に退屈だろうと想像します。退屈さは人に対しても自分に対してもサディスティックになる隙を与えますから、満たされないという至極ありふれたことに、あまりに真面目に悲しんでしまうような青春を送らなかったことは、私が38歳という間抜けな年齢まで死なず生き延びたことと関係しているわけです。
「すべての青春がパセティクな色彩をおびるのは、むりで絶望的な試みの犠牲(筆者注:レヴィ=ストロースの表現)をその本質として所有しているからなのである」