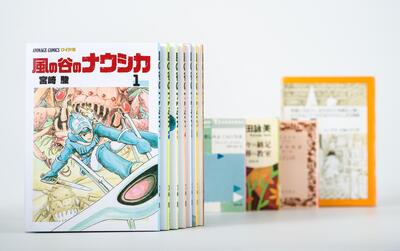鈴木涼美 ピンサロ嬢のお姉ちゃんの強くて美しい魂は、最も汚れ蔑まれる場所で咲く(西原理恵子『ぼくんち』を読む)
多くの人はそんなに強くないけど
薄暗いピンサロで汚いおじさんを相手に商売するお姉ちゃんは、兄弟にそう教えたように、自分もいつも笑い顔で過ごしています。この町の女の人には娼婦や飲み屋の女が多く、みんな男には騙されたり逃げ出されたりしてばかりで、「フツー」の暮らしや「しあわせ」は、本気で願えば願うほど、抗えない現実に対処できなくなるから、夢想はしつつもあまり繊細にならずに、神経を鈍化して鈍化して、自分の傷にも人の傷にも、人間の死にも、鈍感になって生きています。ただ、このお姉ちゃんは神経を鈍化せずに、高貴な魂と知性を維持しながらドブのような町で暮らす稀有な人です。先に引いた『白痴』と同じドストエフスキーの『罪と罰』に、自己犠牲的な精神性で生きる娼婦のソーニャが出てきますが、ソーニャに日本人の顔があるなら、このお姉ちゃんのようであるかもしれません。お姉ちゃんは献身的に兄弟の面倒を見て、母の借金を返し、店の女の子にお金を貸したまま逃げられたり、仲良くなった男が職場で盗みを働いて遠くへ逃げてしまったりして生きています。
お姉ちゃんは知性を鈍化させずに生きているので、この町にいる限り、人はそう簡単に「しあわせと遠い生き様」からは抜け出せないことを見抜いています。だから最後には、主人公のぼくを町の外へ逃す決断をするのですが、自分はこの汚くて貧しい町に止まります。多くの、このお姉ちゃんよりはよほど幸運な境遇にいる人にとって最も困難な自分の人生の受容を、どうしてこのお姉ちゃんはできてしまうのか、これほど現実に強く、どうして何も鈍化せずにいられるのか、作品の中で解き明かされることはありません。多くの人はそんなに強くないから、傷つけられるのに慣れてしまえば自分が傷つけることにも慣れてしまうし、自分の運命を受け入れられないし、汚い場所にいればいるほど、自分自身の魂も汚してしまわなければとても耐えられないのが普通だと私も思います。汚いところにこそ美しいものがあるのではないかという予感は、多くの人が持つところですが、実際は、汚いところには、汚さに耐えるために汚くならざるを得なかった汚い人たちが多くひしめき合っているものです。
それでも、このお姉ちゃんのようなありえないほど強くて美しい、高貴な魂があるとしたら、それはやはり綺麗な場所に育つことなんてあり得なくて、最も汚れ、蔑まれ、神様が与えてくれるものはいずれやってくる死だけだというような場所にしか咲かないのではないか、とも思うのです。