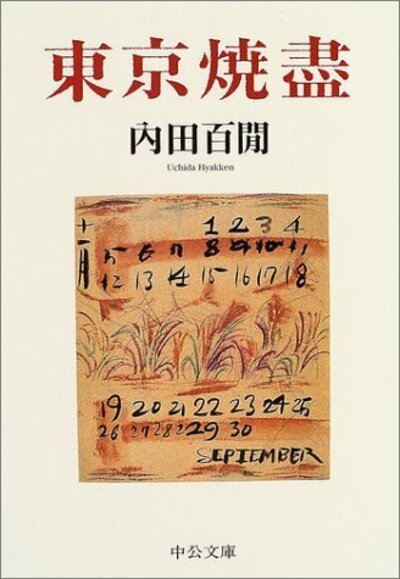「ささやかな差し入れに喜々として暮らした、反骨の人」畑中三応子

内田百閒『御馳走帖』
内田百閒『東京焼盡』
中公文庫は、食の名随筆が充実している。近現代の食の変遷についてあれこれ書いている私にとって、好きなだけでなく、史実を確かめるのに欠かせないのが、内田百閒の『御馳走帖』だ。
たとえば「牛乳」。近代酪農は明治のごく初期、東京都心部で発祥したが、牛乳を飲む習慣が百閒の郷里の岡山に伝わったのは、やっと明治30年前後。飲むと穢れると忌み嫌われた牛乳の普及には時間がかかったこと、しかし子どもの成長に役立つ健康飲料だと認識されていた様子がありありとわかる一篇だった。
太平洋戦争下の食を書いたときは、『東京焼盡』を資料として使わせてもらった。「本モノノ空襲警報」が初めて鳴った昭和19年11月1日から翌20年8月21日まで、文字通り東京が焼き尽くされて一面の焦土になるまでの日記である。
警戒警報が鳴って身構えていると解除になり、いったん寝てうつらうつらしていたら空襲警報ですぐ起こされ、どすんどすんと地響きが何度も聞こえる。こんなのが毎日なのだから、よく正気を保てたものだと読んでいるこちらが恐くなる。いまウクライナの人々、内戦や紛争が続く世界の各地では、これが日常になっているのだと思うとやるせない。
そんな生活でも、百閒の筆からは一流のユーモアが香る。食べるものに不自由し、栄養不足で脚が腫れてきても、無類の酒好きだから麦酒や焼酎にありつけるとご機嫌。家が焼けた空襲のときも最後に残った酒1合を忘れず携帯し、逃げ廻る途中に時々飲み「こんなにうまい酒は無いと思つた」ぐらいなのである。
5月16日「四谷駅の麹町口の軒に今年も燕が巣をつくり今日見たら卵を温めてゐるらしい。ぐるりが廃墟になつたので今年は来るか知らと心配いてゐたが今迄通りやつて来て先づ安心した」。ほっとする、こんな日もある。
5月18日「気やくその悪い大政翼賛会が解散する事になつた由。新聞記事を読みて胸のすく思ひなり。その後出来た文学報国会も勿論無くなるであらう」のところでは、思わず喝采した。文学報国会は大政翼賛会文化部傘下の団体で、当時の有力作家の多くがメンバーになり、文学者大会や講演会の開催など、すすんで戦争協力をしていたが、百閒はいっさい関係しなかった。もしかして活動すれば食料も酒も便宜を図られたかもしれないが、弟子や知人からのささやかな差し入れに喜々として暮らした。反骨の人である。
そんな百閒も8月15日、戦争終結の詔書を聞いたときは「熱涙滂沱として止まず。どう云ふ涙かと云ふ事を自分で考へる事が出来ない」となった。それは、安堵の涙だったのか、むなしさの涙だったのか。綴られた294日の記録からは、空襲下のこの日常だけは書き残しておかなければという強い意思を感じる。『東京焼盡』は、静かな反戦文学である。
畑中三応子さん