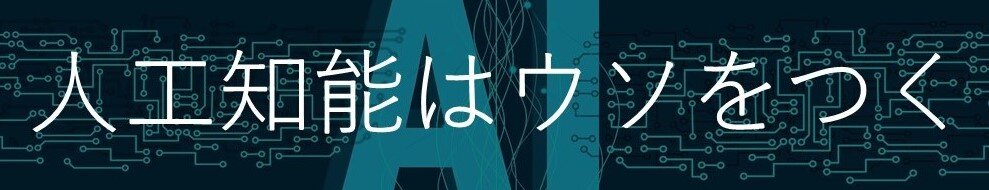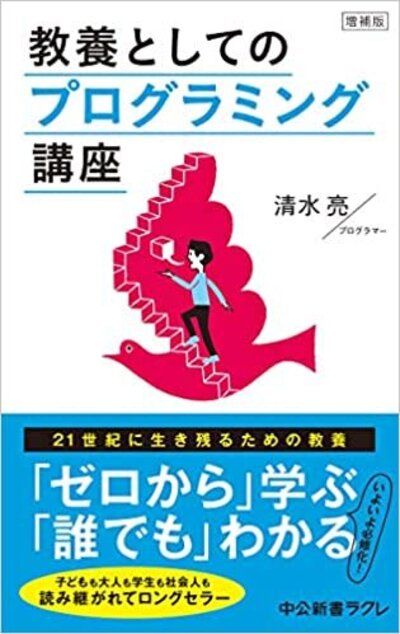GPT以後「知識の集積地」としてのネット空間は汚染されていく。私たちはいつまでWikipediaを信用できるのか
人工知能はウソをつく【第1回】
清水亮
いつまでネットを無条件に信用できるのか
そういう自分さえ、最近はGPTなしでは原稿を書くことさえ億劫になることがある。
専門的な知識さえもっていれば、GPTが出力した文章のどこまでが嘘でどこからが本当かはわかる。しかし専門外のこととなると自信はなくなる。
なおこの原稿は久しぶりにGPTを一切用いずに書いている。むしろ新鮮なくらいだ。
今、GPTが検索エンジンを参照できるようにしてもっと「正しい」ことをしゃべらせるようにしようという動きもある。しかし、検索エンジンの検索結果そのものが汚染されれば、もはやこれに対抗することはできなくなる。
ネットが無条件に信用できるのも、あと数年が限界かもしれない。いやそれとも、とっくに信用するに足りないものになっているのか?
連載を通じて、その行く末を見守っていきたい。
連載『人工知能はウソをつく』最新記事

「街に失業者があふれようがおかまいなし」ビッグテックがAI開発に全力を注ぐ真の理由とは..「貧富の差」「モラル」を無視して進む<人工知能民主主義>に希望はあるか

清水亮「AIの世界で日本は戦えていますか?」と問われて。最大のチャンスを逸した我々は「竹槍で世界に挑んだ」歴史を笑うことなどできるだろうか

清水亮 企業の不正が世間を騒がせた今年「AI」を社長にしてみた。AIの経営判断は<残酷>だがほとんどの場合<人間よりマシ>である
増補版 教養としてのプログラミング講座
清水亮
もの言わぬ機械とコミュニケーションをとる手段「プログラミング」。その歴史から簡単な作成、生活に役立つテクニックなどを網羅し、たった一冊でプログラマーの思考法を手に入れることを可能としたのが『教養としてのプログラミング講座』だ。「もはやそれは誰もが学ぶべき教養」というメッセージを掲げたロングセラーをこのたび増補。ジョブズにゲイツ、現代の成功者はどんな世界を見ている?
清水亮
新潟県長岡市生まれ。1990年代よりプログラマーとしてゲーム業界、モバイル業界などで数社の立ち上げに関わる。現在も現役のプログラマーとして日夜AI開発に情熱を捧げている。『教養としてのプログラミング講座』(中央公論新社)など著書多数。