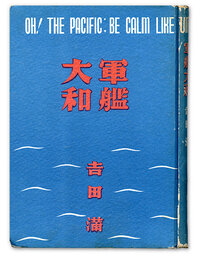橘玲 進化論がもたらす「知のパラダイム転換」 自然科学は人文・社会科学を呑み込むのか
編集者としての体験
――大学卒業後、橘さんは出版業界に足を踏み入れます。編集者時代の読書習慣はどのようなものでしたか?
大学は4年で卒業しましたが、まったくの落ちこぼれで就職活動もせず、年明けになってから新聞の三行広告の求人に応募して新橋の小さな出版社に入れてもらいました。そこでたまたま同じ大学出身だった同僚に「思想とか哲学とか、なんでそんなくだらないものばかり読んでいるの?」とハードボイルド小説を教えられ、レイモンド・チャンドラーやローレンス・ブロックなどにハマった時期もありました。
その後、友人とつくった編集プロダクションをつぶしたあと、25歳で宝島社に拾われ、10年ほど『別冊宝島』と『宝島30』の編集に携わりました。そもそも編集者って、本を読むのが仕事ですよね。ある著者に原稿執筆やインタビューの依頼をするならば、最低でも直近の2~3冊は読んでおかないと話にならない。読書は趣味というより、仕事と一体化していったように思います。
――『別冊宝島』にしろ『宝島30』にしろ、扱うテーマは政治問題からサブカルチャーまで幅広いので、橘さんの読書領域も半ば強制的に広げられたのでは?
そうですね。毎月どこかからテーマを探してこないといけなかったので、それまであまり縁がなかったヤクザもののノンフィクションなども読むようになりました。
――90年代になると、ドラッグや死体、変態性欲などを扱ういわゆる「鬼畜系文化」が流行します。その代表的雑誌である『危ない1号』を創刊した故・青山正明さんとも橘さんはお付き合いがありましたが、当時の鬼畜系文化をどうご覧になっていましたか?
青山さんは同人誌時代から知っていて、編集者としてもライターとしてもスゴい才能だと思いましたが、鬼畜系には正直なところ「何がそんなに面白いの?」という印象がありました。ドラッグにしても、レイヴにしても、ある意味、60年代のカウンターカルチャーの焼き直しですよね。エクスタシー(MDMA)をキメてハウスやトランスで踊るのと、マリファナを吸いながらグレイトフル・デッドのライヴで踊るのと、どれほどの違いがあるのか。
それを今の言葉で言うならば、人間には「進化論的制約」とでもいうべきものがあって、ほんとうに新しいものなどめったに出てこない。あとは、前の世代がやったことを外見を変えて繰り返しているだけです。
ドラッグにしても、トリップできそうなものは60年代のヒッピーたちがすべて試している。セックスにしたって、ヒッピーコミューンのフリーセックスまで行き着いているのだから、そこから先は行き止まりですよね。
そうやって60年代の終わりまでには、多くの若者たちが依存症になり、精神病院に送られ、あるいは自殺して、その死屍累々の上に今のサブカルチャーがつくられた。その意味で鬼畜系は、犯罪性を強調することで差別化しようとしたところに危うさがあったのかなと思います。