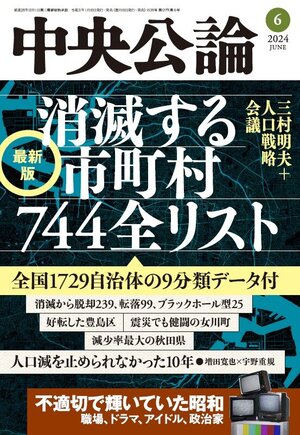『在日米軍基地──米軍と国連軍、「2つの顔」の80年史』川名晋史著 評者:多湖 淳【新刊この一冊】
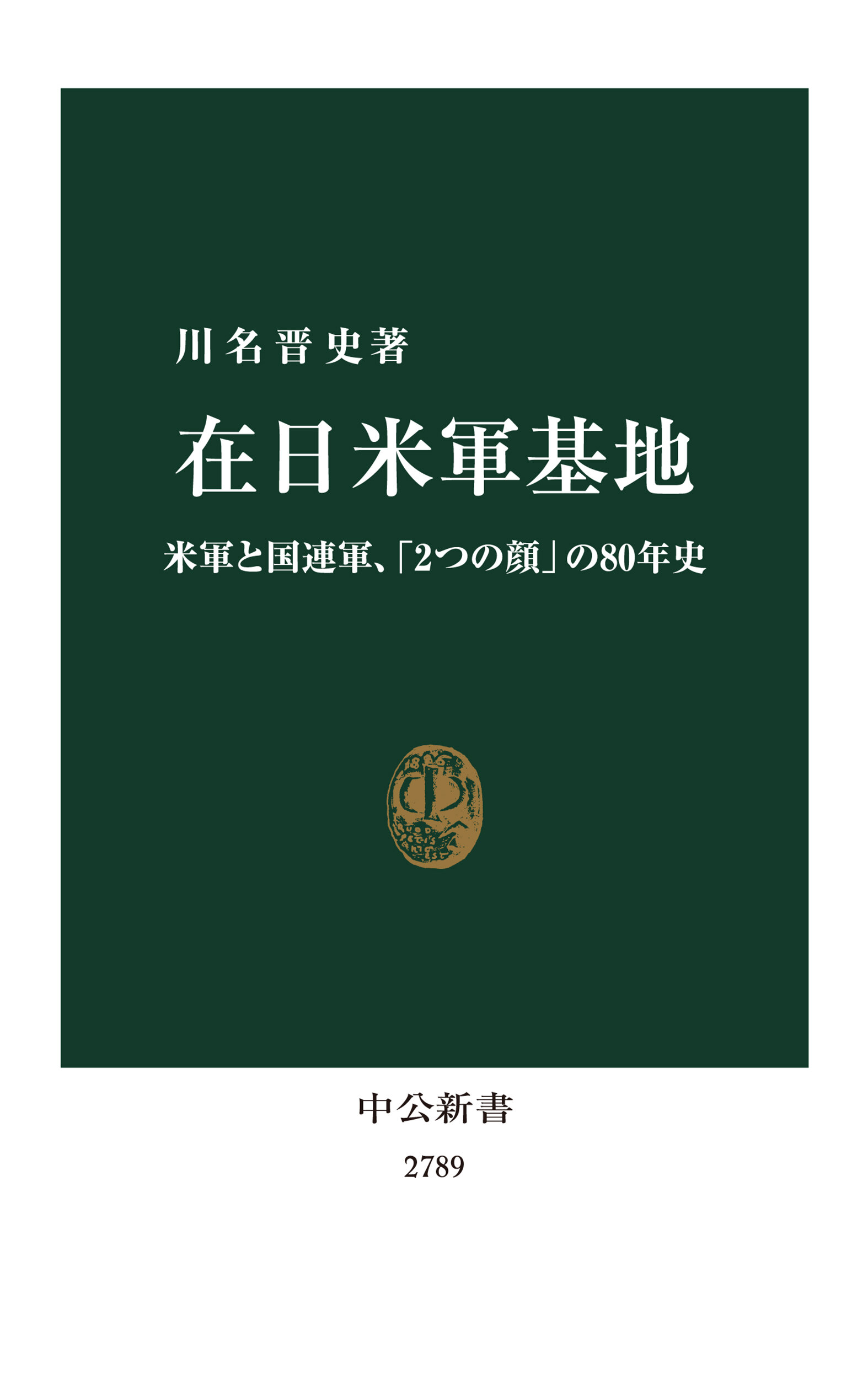
評者:多湖 淳(早稲田大学政治経済学術院教授)
評者は知的生産を英語の国際政治学の世界で行うタイプの研究者である。しかも、ある事情から日本語での執筆はやめようと決めていた。しかし、今回の書評はあえて例外として書いている。それは、本書が広く読まれねばならないからである。
日本の安全保障が岐路に立つ中、米国政府・米軍と日本が安全保障のための基地をめぐる約束をどのように結び、その約束が制度としていかに定着し、そして個別の基地政策がどうして今のようになっているのかが浮かび上がる。物事が「なぜそうなるか」でなく「どうなっているか」に焦点を当てた歴史分析を、専門用語では記述推論と呼ぶが、そのお手本になる秀作である。研究者向けの書物でないレーベルの中公新書で、この水準の著作が読めるのは幸運だ。
本書の大事な発見は、朝鮮戦争の際に創設された朝鮮国連軍の枠組みが、基地使用に関する日本政府との事前協議をバイパスしうる制度として米国政府から理解され、重視されたという点にある。国連軍としての駐留が継続的にできるよう様々な手が講じられ、多国間の事実上の有志連合が今日まで継続してきたのである。国連軍が消滅すると事前協議を回避する手立てがなくなる。このため、儀仗隊や限られた数の将校でよいので日本に兵員を派遣するよう各国に働きかける米国政府、それに応える国の存在など、実直な史料収集と読み込みこそが可能にする記述推論がこの本にはある。
そして、そもそも終戦後から1960年代まで本州の基地のほうが圧倒的に多かったのに、なぜ米軍基地が沖縄に集中していくのか、さらには普天間移設問題がどうしてこんなに混乱しながら推移するのかについて、独自の見解が示される。現在の辺野古への移設計画の青写真は古くから存在していたという指摘も興味深い。
著者は基地問題の研究者として、国内の基地だけを扱うのではなく、広く国際比較する仕事をしてきた。基地比較の研究書を日本語でも英語でも出しているリーディング・スカラーだからこそできる「比較」という軸の存在も、本書の価値をより高めている。
なお、評者と著者は東京大学名誉教授・青山学院大学名誉教授である故・山本吉宣(よしのぶ)先生の兄弟弟子の関係にある。その事実は評者の評価を割り引いていただくために述べておくべきだろう。よって贔屓目がゼロだとは言わない。同じ門下であるからこそ評価すべき事項が目につくのかもしれない。
しかし、そういうことは脇に置いたとしても、日米安保体制を深く理解し、今後の日本の安全と地域の平和をどう守ることができるのかを考えることは、こういった良質の記述推論を読んで現在地を把握してこそ可能になる。自分のいる場所がわからなければ、次の手をめぐる方針は立たない。
最後に、本書は国際政治の中で日本が韓国といかに運命共同体であるのかを示唆している。北朝鮮というならず者国家を隣に置いて、徴兵制を維持する韓国に、日本人は感謝するほかない。米国政府も日本政府もそういった東アジアの国際政治の現実を踏まえ、国連軍を理解し、基地政策を動かしてきた。単に基地の話にとどまらない、地域の国際政治を考えるにあたって必読の書である。
(『中央公論』2024年6月号より)
◆川名晋史〔かわなしんじ〕
1979年北海道生まれ。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。青山学院大学大学院国際政治経済学研究科博士後期課程修了。博士(国際政治学)。専門は米国の海外基地政策。著書に『基地の政治学』(佐伯喜一賞)など。
【評者】
◆多湖 淳〔たごあつし〕
1976年静岡県生まれ。東京大学教養学部卒業。同大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。博士(学術)。著書に『武力行使の政治学』『戦争とは何か』など。