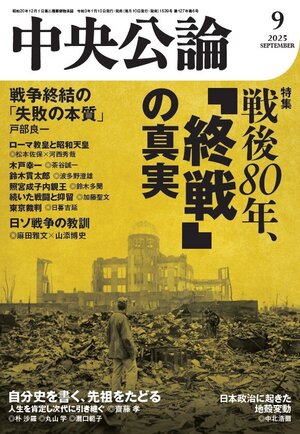自治体を疲弊させる「現金給付」に異議あり

毎年の「現金給付」で 疲弊する現場
――この6月11日、政府が進める現金給付に対し、その非効率性と自治体の疲弊を訴えたX(旧ツイッター)の投稿が話題になりました。千葉市長時代の経験からの発言とのことですが、具体的に自治体にはどのような負担が生じるのでしょうか。
制度設計にもよりますが、2020年にコロナ禍で実施された1人一律10万円を支給する特別定額給付金を例に説明します。これが最もシンプルで負担としては比較的「マシ」なのですが、それでもまず基準日時点での全対象者のデータを抽出することから始まります。
また政府が個人に給付するのは「贈与契約」にあたるので、対象者全員に受け取りの意思確認をする必要もあります。申請書を郵送し、必要事項や受け取りの口座番号などを記載したものを返送していただかなければならないわけです(郵送申請の場合)。さらに返送された大量の申請書の確認作業と入力作業を逐一行い、それを金融機関に渡すまでが一つの大きな流れです。
それと並行して必要なのが、コールセンターの設置。多くの問い合わせがあるので、想定されるQ&Aマニュアルの作成や民間事業者への業務委託などの事務が発生します。
こうした一連の膨大な作業があるわけです。しかもこれは一律10万円給付のケースです。ここに「非課税世帯は上積み」とか、「子供1人あたりいくら」といった条件が加わると、より複雑な作業が発生します。これを、すべての市区町村がバラバラに行っているのが現状です。
――それらの仕事は、市区町村のどの部署の方が担当されるのですか。
もちろん専業の部署はないので、各部署から知識や経験のある職員を少しずつ集めて特別部隊を作るわけです。しかし今は自治体職員の採用も難しく、むしろどんどん転職してしまう時代です。つまり、もともと人手は余っていません。その状況下でさらに通常業務から離れてもらうわけですから、現場が疲弊するのは当然ですよね。
しかもこれが、もう毎年のように行われているわけです。とりわけひどかったのが、昨年6月に岸田(文雄)政権下で実施された「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」。給付と減税を同時に行うとなると、対象者ごとにきわめて複雑な計算が必要です。その上、昨年10月の衆院選までに〝減税感〟を出したいとのことで、とにかく急かされました。結局、とりあえず減税を先行させて過不足を後の徴税で調整することになったのですが、実は今でもその処理が終わっていません。これは私の知る限り、最悪の政策です。
そこに今回、石破(茂)政権は参院選の公約として「一律2万円給付」を掲げたわけです。さらに住民税非課税世帯の大人にはプラス2万円、18歳以下の子供にもプラス2万円と複雑化しました。参院選後に臨時法案を作り、補正予算を組んで遅くとも年内には配るんだと。もう無茶苦茶です。
正直なところ、「いい加減にしてくれ」と声を大にして言いたい。市区町村の悲鳴と怨嗟(えんさ)の声に、もう少し耳を傾けていただけないものかと思います。
構成:島田栄昭
(『中央公論』9月号では、この後も自治体の負担を減らすために必要なこと、国会議員や官僚が苦境に反応しない構造、現金給付自体への見解について語っている)
1978年生まれ。2001年、早稲田大学政治経済学部卒業、NTTコミュニケーションズ入社。07年から千葉市議会議員。09年、千葉市長選挙に当選(31歳)、政令指定都市では歴代最年少市長となる。13年に再選、17年に3選。21年、千葉県知事選挙に当選、25年、再選。