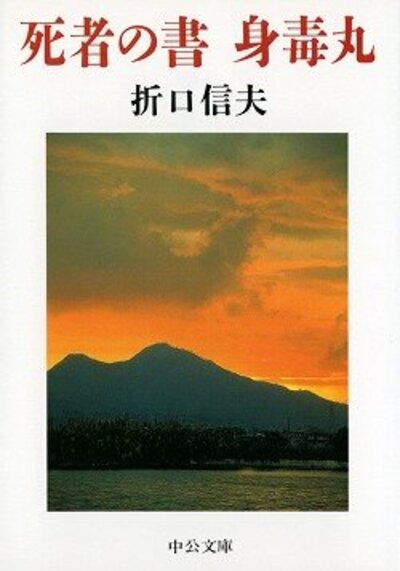「あゝ耳面刀自」小池陽慈

折口信夫『死者の書』(現在は新版『死者の書 身毒丸』)
「した した した。」――この異様な言葉の連なりが擬音語であるらしいことは、それに続く「耳に伝ふやうに来るのは、水の垂れる音か。」という一文によって理解される。なるほど、「した」と「した」との間に置かれた空白は、一粒ひとつぶの水滴が垂れる、その時間の間隔を表しているのだ。
それにしても、なぜ語り手は、「水の垂れる音か」と言うのか。つまり、疑問の終助詞「か」をもってこの文を閉じるのか。
語り手は、ここで、「彼(か)の人」の聴覚に同一化している。「彼の人」――すなわち、大津皇子(おおつのみこ)に。折口信夫の著した物語「死者の書」の冒頭は、非業の死をとげた大津皇子が、巌の墓穴の奥底で悠久の眠りから目覚める、その様子を描く。だから、その耳――語り手が同化する大津皇子の耳は、いまだ曖昧模糊たる意識のまま、聴覚を刺激する音のなんたるかを判然とは理解していない。したがって、「水の垂れる音か」、そう語るのである。
活字と活字の間の空白。そして、たった一文字の助詞。こうした細部にまで注意の払われる、緻密で張りつめた文体が紡ぐ緊迫感のなか、厳かに発される「彼の人」の声。
「あゝ耳面刀自(ミミモノトジ)。」
「耳面刀自」とは、在りし日の大津皇子の懸想人であり、今、長き眠りから覚めた皇子が、何よりも真っ先に思い出した言葉が、その名であった。「彼の人」は、「耳面刀自。おれはまだお前を......思うてゐる。」と続ける。
「あゝ耳面刀自。」――これほどに濃密な愛の言葉も、なかなかにないだろう。そうしてそんな愛の言葉が、私の脳内では、ぼそぼそのっそり、それでいて野太く響く。おおよそ還暦の頃の、男性の声で。
東郷克美先生は、母校の恩師であり、その先生のご講義「近代文学演習」で扱った教材が、中公文庫の『死者の書』であった。当時はまだ旧版で、カバー画はエジプトの壁画であった。新版『死者の書 身毒丸』では、二上山の写真に差し替えられている。
先生は、ご講義のなかで、よく朗読をなさった。もちろん、「あゝ耳面刀自」、とも。
「おい、君たち。ちょっと飲みに行かないか」「私はねぇ、こう見えて健脚でね」――そうした先生の口癖と、全く同じトーン、抑揚、声色で発された、「あゝ耳面刀自」。あれから約二十年、今こうして「死者の書」を紐解き、古代のロマンを味わいながらも、行間からは、あのオンボロ校舎の教室や、先生に連れていってもらった高田馬場の居酒屋の空気が漂ってくる。
「近代文学演習」を受講した翌年、私は、大学院に進み、東郷先生の研究室でご指導を賜った。けれども不義理を働き、中途で退学してしまった。
数年前、一冊の本を著し、それを先生にお送りした。謝罪の言葉も添えた。すぐにお返事を頂戴した。あたたかな言葉が綴られてあった。私だけの大切な宝物なので、その内容はここには記さない。そのお言葉が、やはりあの、「あゝ耳面刀自」の声で再生されたと言うにとどめておく。

小池陽慈さん