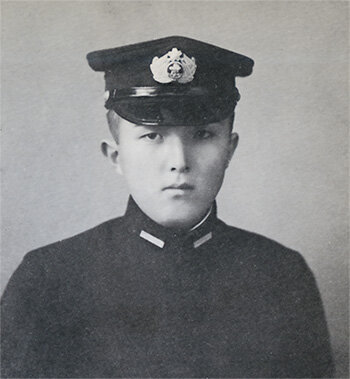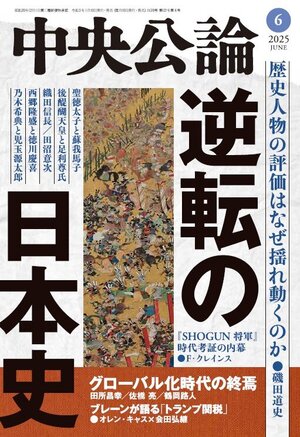八月十五日以後、小林秀雄の「沈黙」と「戦後第一声」(中)
「このなかに八首だけよくない歌がある!」
吉野に原稿料を払った夜、小林の家で林房雄夫妻、永井龍男、吉野とその知人が集まった。酒盛りである。その場で、吉野の知人の「いゝ時代が来たとの言葉」に、「小林氏強く反駁し」ているのが、小林らしい。林房雄は「東条[英機]を弁護するなどに快弁ふるふ」と例の調子で盛り上がった。「小林氏、余の歌稿中、「仏手」の数首はやや劣るかといふ。蓋し適評ならん」と、吉野は小林の批評眼に納得した。
吉野は戦後にできた鎌倉アカデミアで教えるのだが、その時の教え子に山口瞳がいる。山口は『小説・吉野秀雄先生』で、こんな「伝説」を紹介している。
「『創元』は定価百円という当時としてはすこぶる豪華な雑誌であった。舞台もよかった。雑誌も、先生の歌も、すぐに評判になった。/この歌に関して、次のような伝説が残っている。/『創元』の実質的な編集長であった小林秀雄さんは、この原稿を受けとって、読みおわるなり、凄い勢いで山を駈けおりてきて、吉野先生の門を叩き、こう言ったというのである。/「このなかに八首だけよくない歌がある!」/つまり、あとの歌は、全部いい、全部傑作であるという意味だったのである」
小林の扇ヶ谷の家はたしかに高い土地だったから、「山を駈けおりて」なのだろう。吉野の「短歌百余章」は「創元」第一輯に十二頁を費やし、ゆったりと組まれた。これも最大限の遇し方と思われる。「短歌百余章」は、四人の子を残して昭和十九年(一九四四)八月に病死した妻を悼んだ挽歌を中心に構成されている。
古畳を蚤のはねとぶ病室に汝が玉の緒は細りゆくなり
服ますべき薬も竭きて買ひにけり官許危篤救助延命一心丸
氷買ふ日毎の途にをろがみつ餓渇畠の六体地蔵
九州を敵機の襲ふゆふまぐれ妻の呼吸のやうやくけはし
今生のつひのわかれを告げあひぬうつろに迫る時のしづもり
遮蔽燈の暗きほかげにたまきはる命尽きむとする妻とわれ
葬儀用特配醤油つるしゆくむなしき我となりはてにけり
よろめきて崩れおちむとするわれを支ふるものぞ汝の霊なる
真命の極みに堪へてししむらを敢てゆだねしわぎも子あはれ
これやこの一期のいのち炎立ちせよと迫りしわぎもよ吾妹
ひしがれてあいろもわかず堕地獄のやぶれかぶれに五体震はす
たちかへる年の旦の潮鳴りはみ国のすゑのすゑ想はしむ
なお、『中央公論』6月号で「昭和二十年の小林秀雄」と題して、本連載(1~3回)の縮約版が先行公開されています。
※次回は6月25日に配信予定です。
1952年東京都生まれ。慶應義塾大学国文科卒業。出版社で雑誌、書籍の編集に長年携わる。著書に『江藤淳は甦える』(小林秀雄賞)、『満洲国グランドホテル』(司馬遼太郎賞)、『小津安二郎』(大佛次郎賞)、『昭和天皇「よもの海」の謎』、『戦争画リターンズ――藤田嗣治とアッツ島の花々』、『昭和史百冊』がある。