苅谷剛彦×橘木俊詔 英語支配と米国モデルに大学は抗えるか ――入試大混乱時代のエリート教育論(下)
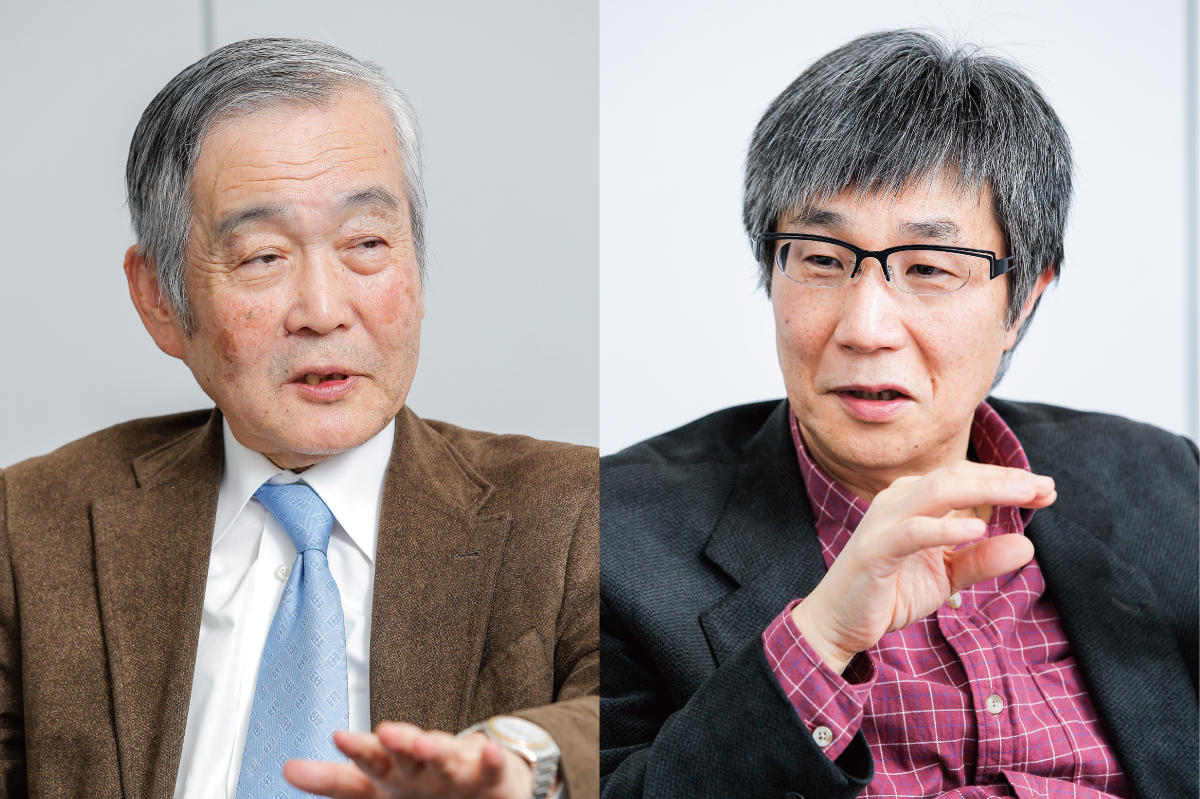
入試改革を考えるには、欧米各国の事例を知ることも参考になるだろう。そこで、イギリスのオックスフォード大学で教鞭をとる苅谷氏と、フランスのINSEE(国立統計経済研究所)とOECDパリ本部勤務経験のある橘木氏の二人による対談を二回に分けてお届けする。今回は後編。
なお、この対談は昨冬の入試大混乱の直後に行われたものの再録になるが、二人の直近の大学論は、苅谷剛彦著『コロナ後の教育へ――オックスフォードからの提唱』、ならびに橘木俊詔著『大学はどこまで「公平」であるべきか――一発試験依存の罪』(ともに中公新書ラクレ)をご参照いただきたい。
エリート教育のホンネとタテマエ
苅谷 日本の受験システムの問題点のひとつは、結局、実態としてはみんな認めているのだけれども、政策論議の中では「エリート主義」がなかなか認められないことだと思います。
東大と京大の二次試験の問題を見れば、どういう能力を持った人がこれらの大学に合格するかがわかります。では、そうした実態を何と呼ぶか。問題はそこです。日本ではあえてそれを単なる偏差値の高さ=知識の量だとみなす。実際は、二次試験の結果には、単なる知識の量だけでない、それとは別の能力の質的な意味が含まれている。だがそのようには見ない。
橘木 ものすごく良いご指摘です。日本はやはり表面的にはエリート主義を排除する社会です。もちろん実質的にはエリートはいるんだけれども、表面的には「エリート」とは言わない。少なくとも日教組はこれまでエリート主義教育はだめだとずっと言ってきましたからね。
一方、イギリスやフランス、アメリカもそうですが、エリートが出てくるのは社会の必然だと、エリートの役割というものを一定程度認めている社会だと言えます。
苅谷 日本がエリート主義を排除するようになったのは戦後のことで、戦前は超エリート主義社会でした。戦後、民主主義がある種の理想主義として入ってきて、それが平等主義とともに戦後の日本社会形成の両輪となり、これらを通じて新しい国民を育成していくんだとなったとき、エリート主義排除が始まった。
橘木 ただし、そうは言っても戦前からの名残りは今なお実質的には残っていますね。
苅谷 そのとおりで、現に大学の階層性(大学格差)は今も変わっていないでしょう。これってどういうことかというと、要するに人々の認識の中ではエリート主義は暗黙のうちに認められている。けれども、公式の議論の場ではなかなか認められない。日本の大学の二次試験は実質エリート主義的な選抜を大っぴらにやっているということです。
橘木 たしかに、最初のほうでも言いましたが、日本の国公立大学と一部の私立大学が実施している、センター試験プラス個別試験という二段階方式は、フランスのグランゼコールやイギリスのオックスブリッジなど名門エリート校が独自に行っている選抜方式と同じですからね。
苅谷 東大、京大に限らず旧帝大の二次試験を見ても、あれだけ記述式の問題を出して、採点する先生たちがいくら厳密に採点していると言っても、そこには主観的な評価が含まれます。どうしたってブレは生じる。でも、そういう大学の記述式問題だったら、そこの先生たちの採点を信頼しようという、これも暗黙のうちのコンセンサスがある。
だから過去脈々と、戦後の教育改革を経ようが、受験システムがいろいろ変わろうが、旧帝大を含むトップレベルの国立大学では、長年、記述式の問題を出して、各大学は自分のところに合う学生を選抜してきたわけです。そういう大学を志望する受験生にとっても、受験勉強は二次試験対策が中心です。そうした選抜の仕組みが続いてきたことは、じつは結果的にエリート主義を認めていることと同じなのではないでしょうか。







