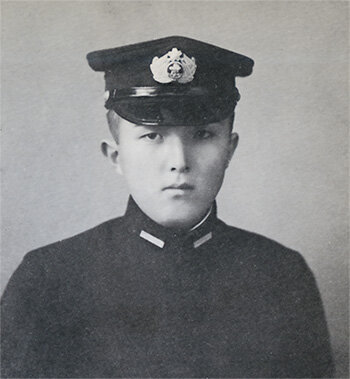小林「武蔵」の「放言」と、大岡「老兵」の復員(上)
【連載第四回】
平山周吉(ひらやま・しゅうきち)
「放言」が深化した小林の昭和二十年代
占領の終わりが近づき、講和問題が大きくクローズアップされた昭和二十六年(一九五一)の正月に「大阪新聞」(1・5)に発表された「独白」では、さらに苦みが加わっている。
「戦争放棄の宣言[憲法第九条]は、その中に日本人が置かれた事実の強制力で出来たもので、日本人の思想の創作ではなかった。私は、敗戦の悲しみの中でそれを感じて苦しかった。大多数の知識人は、これを日本人の反省の表現と認めて共鳴し、戦犯問題にうつつを抜かしていた。/当時、私は或る座談会で、悧巧な奴はたんと反省するがよい、私は馬鹿だから反省なぞしない、と放言し、人々の嘲笑と非難を買った。私は、自分の名状し難い心情を語る言葉に窮しただけで、放言なぞする積りはなかったのである。今日になっても同じ事だ。私の心は依然として乱れている」
この時期の講演録「私の人生観」、「政治と文学」は、いずれも「放言」の続きという性格が強い。特に長い講演録(これらも講演に大幅に加筆した原稿だ)が最終コーナーにいたると、その感が強くなる。小林秀雄の昭和二十年代は、『モオツァルト』、『ゴッホの手紙』、そして『近代絵画』の連載開始に代表されるが、もう一つの大きな流れが、「放言」を深化させる過程だったのではないか。
※次回は7月25日に配信予定です。
平山周吉(ひらやま・しゅうきち)
雑文家
1952年東京都生まれ。慶應義塾大学国文科卒業。出版社で雑誌、書籍の編集に長年携わる。著書に『江藤淳は甦える』(小林秀雄賞)、『満洲国グランドホテル』(司馬遼太郎賞)、『小津安二郎』(大佛次郎賞)、『昭和天皇「よもの海」の謎』、『戦争画リターンズ――藤田嗣治とアッツ島の花々』、『昭和史百冊』がある。
1952年東京都生まれ。慶應義塾大学国文科卒業。出版社で雑誌、書籍の編集に長年携わる。著書に『江藤淳は甦える』(小林秀雄賞)、『満洲国グランドホテル』(司馬遼太郎賞)、『小津安二郎』(大佛次郎賞)、『昭和天皇「よもの海」の謎』、『戦争画リターンズ――藤田嗣治とアッツ島の花々』、『昭和史百冊』がある。