「新夕刊」創刊と、謎の社長「高源重吉」との関係(下)
格別に大事な「食客」の扱い
門屋博の林房雄追悼文に戻れば、門屋は上海にも家を借りていた。
「虹口サイドの文路にある景林盧というマンションの一角で、蔣介石が結婚式を挙げたという教会の付属建物で、この頃日本で言うマンションとは比較にならぬ広くゆったりとした間取りだった。南京を引きあげた林や小林秀雄さん達は、此処を根城にして又何ヶ月か暮らされた。私を通じて、当時上海に来ておられた児玉誉士夫さん・岩田幸雄さん、すでに故人になられた吉田彦太郎さん、高源重吉さん達との交流が始まった。私はあまり酒をたしなまないので、そうした心情は判らないのであるが、酒を愛する同志の親和力というものは、不思議なもので、年齢の差や考え方の相違を超えて、その関係は急速に深かまっていった。勿論、お互いに影響し合うところもあったのであろうが、林と児玉さん、岩田さん達のつながりは、林が死ぬまで更らに強い関係となって続いていったのである」
門屋の追悼文は主眼が旧友の林房雄なので、小林の話題は途中から消えてしまう。それでも南京、上海時代の小林についての数少ない証言である。格別に大事な「食客」の扱いを受けて飲み食いする姿はわかるが、いくら想像力を働かせても、その心情に近寄ることはできない。林房雄は戦後初めて高源に会ったと回想しているので、門屋の文章もどこまで信じていいのかわからない。小林が上海で児玉誉士夫と会っていたというのも本当だろうか。そうした数々の疑問は起こるのだが、小林の中国時代はおおまかに想像できよう。「西行」「実朝」を書き上げたあと、小林は戦争の現実から、やはり目をそむけてしまったのか。「その時が来たら自分は喜んで祖国の為に銃を取るだろう」という昭和十五年の講演「文学と自分」での言葉は、小林の胸中に去来していたか否か。戦局の厳しさは、国内にいるよりも外地での方がより身近に感じられただろう。
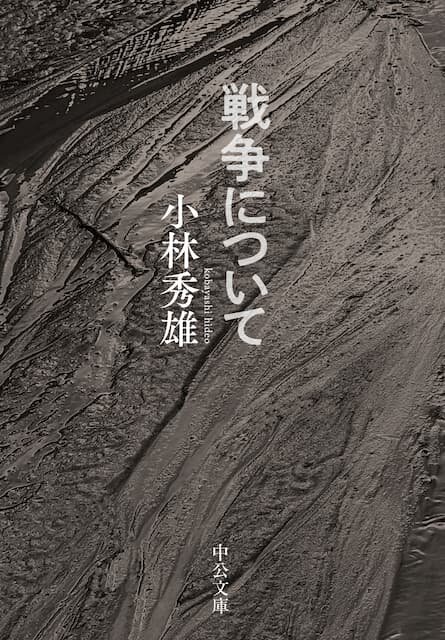 「文学と自分」所収、小林秀雄『戦争について』(中公文庫)
「文学と自分」所収、小林秀雄『戦争について』(中公文庫)







