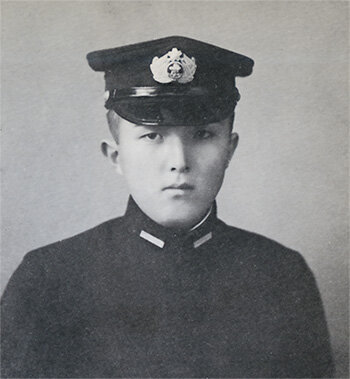「新夕刊」創刊と、謎の社長「高源重吉」との関係(下)
「近代の超克」のメンバー再び
小林秀雄と高源重吉との接点を探してきたが、これ以上は無理だった。『小林秀雄全集』で見る限り、小林が「新夕刊」に登場したのは、座談会一回だけだ(次回に詳述するが、これ以外に座談会をもう一回、さらに原稿を二回発表している)。昭和二十二年六月に掲載されたもののようで、全集では「旧文學界同人との対話」となっている。初出では「幸福について」だったらしい(『小林秀雄全集』別巻)。出席者は河上徹太郎、亀井勝一郎、林房雄、小林秀雄で、林が進行役として喋りまくっているといった感じだ。林は戦争中に、文学者が大戦争の中で、小説以外のことを語れなかったという点を問題にする。「反対するとも、賛成するとも言うものがなかった。知識階級の醜態だね。右が強ければ右に従い、左が強ければ左に従う」と。林の挑発発言に刺激されてか、小林が口を挟む。「そして発言しなかったのが今おれは発言しなかったと言っていばっている」。林「ああ」。小林「しかし歴史の中に生きるということは、そういうことじゃないからね」
林は亀井に向かって「今度は君、問題を出せよ」とけしかける。亀井はここで「近代の超克」を持ち出す。この座談会出席者は、五年前の共同討議「近代の超克」の出席者であるから当然の展開かもしれない。亀井が持ち出し、河上が応じる。
亀井「終戦後、文学上のいろんな評論を読んでみて一番問題になったのは何かというと、近代の超克だと思う。日本には近代というものはなかった。だから、われわれはこれから近代を確立する。人間の解放ということと結びつけて言ってるんだけれども、若い人の評論を見ると、どうして近代を疑惑しないのかと僕は言いたくなる」
河上「われわれは近代の超克と言ったけれども近代というのは世紀末から二十世紀にかけてを言ってるんだろう。これがルネッサンス精神を堕落させたものである、ということなんだ。だから、われわれのやりかけたことは、ルネッサンス運動だったんだよ」
ここから四人のボルテージは上がっていく。小林は本阿弥光悦と俵屋宗達の名を出して、「幸福論」を展開する。「幸福」という思想が現代日本でも、近代の全世界でも栄えないのはなぜか。「幸福というものは全人的でしょう」、「全身の緊張を要する一大事業ですよ」、「社会とか国家とかいうようなものを予想しなくてもいい思想ですよ。もしも完成すれば自ら社会あり、自ら友人あり、という思想ですよ」、「これを破壊したものは近世のブルジョア社会ですよ」。タイトルが「幸福について」ならば、小林が一番言いたかったことはこのへんの言葉にあるのだろうか。
亀井勝一郎の日記を見ていたら、前年の五月に、このメンバーは鎌倉極楽寺の高源重吉の大邸宅に集まり、飲み明かしている。五月十九日の日記。
「文学――この生れたるもののめざすところは美である。或は哀しき幸福。/一昨日から昨日にかけて小林、林、河上等と飲む。高源氏宅にて非常に飲む。/安易なことをやってはいけない安易なことをやっているのがいけない、親鸞を誰でもやっている、何故恵心僧都を語らぬのか? そう云って小林のこごとをくう。/尤ものことと思う」
※次回は9月29日に配信予定です。
1952年東京都生まれ。慶應義塾大学国文科卒業。出版社で雑誌、書籍の編集に長年携わる。著書に『江藤淳は甦える』(小林秀雄賞)、『満洲国グランドホテル』(司馬遼太郎賞)、『小津安二郎』(大佛次郎賞)、『昭和天皇「よもの海」の謎』、『戦争画リターンズ――藤田嗣治とアッツ島の花々』、『昭和史百冊』がある。