戦後初原稿「政治嫌ひ」が「新夕刊」創刊号を飾る(上)
正宗白鳥に「人生苦」を味わわせる酔漢・小林
昭和二十三年(一九四八)の正宗白鳥との対談「大作家論」では、小林は泥酔してしまう。小林は遺作「正宗白鳥の作について」で、対談の後、鎌倉行の電車に乗ったつもりが、眼が覚めたら東海道線の沼津駅だったという失敗をさらし、さらには白鳥から廻って来た速記録には「内容浅薄」と一刀両断された思い出を語っている。その時、下戸の白鳥の目に、酔漢の小林はどう映ったか。白鳥が小林の酔態を書いた「座談会出席の記」(「文芸」昭和23・11。坪内祐三選『白鳥随筆』講談社文芸文庫に所収)から引いてみよう。場所は「古ぼけた陰気な鰻屋の階上」だった。
「酒が廻るとともに話ははずんだのだが、二人の話は次第に別々になって、座談会の常例であるように、互いに相槌を打って、「私もそう思います。」とか「それには同感です。」とか云うような事はあまりなかった。(略)素面の時には遠慮して云わないような事をつけ/\と云うので、私も普通の座談会と異なり、得るところもあり、面白く思われる事もあった。しかし、次第にうるさくなった。酔っ払いは自分に勝手なことを云うだけで人の事を理解しようとはしないのである。(略)酒は飲めず、胃弱のため料理もあまり食べられない老体の私が、長時間、相手の論鋒をよけ/\腰を据えているのは、これも一種の人生苦ではあるまいか。(略)その夜私は疲れた」
尊敬する文壇の大先輩の白鳥を相手でも、老いた白鳥に「人生苦」まで味わわせるのだから、小林の酒は困ったものである。児玉機関であろうと、正宗白鳥であろうと、無礼講のからみ酒なのだ。「近代文学」の評論家たちが位負けしたのは仕方ないのかもしれない。後年になるが、三島由紀夫の死をめぐって対決となった江藤淳との対談「歴史について」(「諸君!」昭和46・7)での飲酒状況をも付加しておこう。あの対談は小林の定宿である湯河原の旅館「加満田」で行なわれた。小林は「恥ずかしいから一本呑ませてくれよ」と熱燗を女将に所望する。微醺を帯びての対決だったのだ(中公文庫『小林秀雄 江藤淳 全対話』の注参照)。
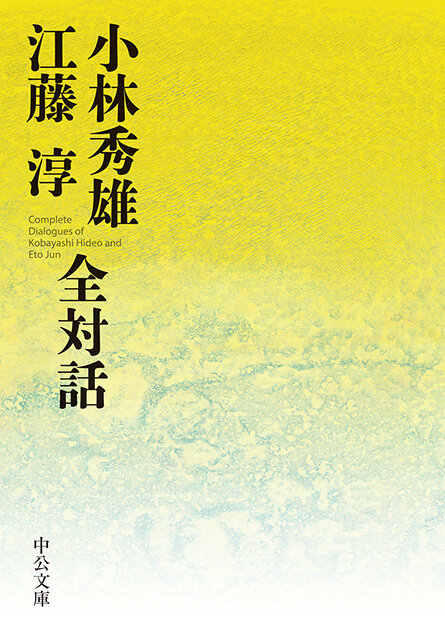 『小林秀雄 江藤淳 全対話』
『小林秀雄 江藤淳 全対話』







