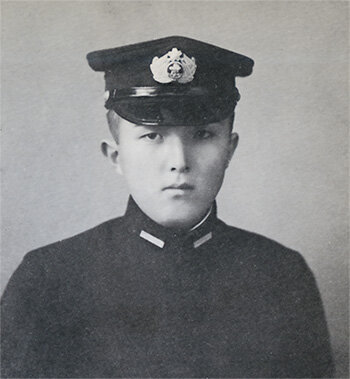戦後初原稿「政治嫌ひ」が「新夕刊」創刊号を飾る(上)
「新夕刊」目録で見つかった小林の未発掘原稿
その事実を教えてくれたのは、大阪大学の斎藤理生教授の「〈資料紹介〉『新夕刊』文藝記事目録(一九四六)――「世にも不思議な新聞社」の輪郭」(「昭和文学研究」90集、2025・3)だった。斎藤は国会図書館だけでなく、横浜の日本新聞博物館が所蔵する「新夕刊」を調べ、文学関係記事の目録を作った(翌一九四七年分は「阪大近代文学研究」23号、2025・3)。両館所蔵を合わせても完璧ではないが、斎藤の目録によって、戦後文学史の小さからぬ穴は埋められた。一番の注目は、小林の「政治嫌ひ」で、それによって、小林の戦後「第一声」の「発せられた時期がくり上がる」と報告されていた。
斎藤がなぜこの調査を思い立ったかというと、それには私の『小津安二郎』という本が関与していた。奇しき縁を感じる。その本の中で、私は小津の未発掘の随筆「映画と連句」を紹介した。この随筆は、「新夕刊」(昭和22・5・17)に掲載されたもので、新聞博物館の倉庫に所蔵されていた紙面から翻刻した。私の『小津安二郎』で「新夕刊」のありかを知った斎藤理生は、サバティカル(長期研究休暇)を利用して、両館に通い、目録を作った。斎藤のブログには、その日のことが報告されている。
「[サバティカル]116日目には、新幹線で上京。主に国会図書館の新聞資料室でマイクロを回す。その間に次男サッカー中に骨折のお知らせが届く。夜、元町中華街で友人と会食。
117日目には、神奈川近代文学館の閲覧室で調べ物。午後、日本新聞博物館。最初に拝見した資料が素晴らしかった。その後も80年近く前の新聞原紙を閲覧して手が黒ずんでゆく。17時までゴリゴリ拝見して新幹線で帰宅」
この「最初」の資料が、小林の「政治嫌ひ」ではないかと思われる。斎藤の調査で、小林秀雄には他にも昭和二十二年(一九四七)正月の随筆、同年夏の座談会、という未発掘原稿があることが確認された(次回で紹介する)。
(引用した「新夕刊」掲載の小林秀雄の文章と発言の探索については、日本新聞博物館の協力を得ました。感謝いたします)
※次回は10月10日に配信予定です。
1952年東京都生まれ。慶應義塾大学国文科卒業。出版社で雑誌、書籍の編集に長年携わる。著書に『江藤淳は甦える』(小林秀雄賞)、『満洲国グランドホテル』(司馬遼太郎賞)、『小津安二郎』(大佛次郎賞)、『昭和天皇「よもの海」の謎』、『戦争画リターンズ――藤田嗣治とアッツ島の花々』、『昭和史百冊』がある。