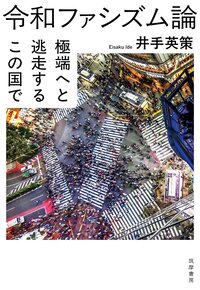単行本『無常といふ事』がやっと出る(一)
【連載第十一回】
平山周吉(ひらやま・しゅうきち)
少なかった初版部数
この時期の本は奥付に印刷部数が明記されているものとされていないものがある。創元社の本で明記されているものの部数をいくつか挙げよう。林房雄『西郷隆盛 九巻 風の巻』一万部(昭和20・10)、菊池正士『物質の構造』第六版五千部(昭和21・4、初版は昭和16)、原随園『ギリシア史研究 第一』第四版二千部(昭和21・6、初版は昭和17)。林のは大長編小説なので、比較の対象にはなりにくい。「近代の超克」に出席した物理学者の菊池正士と、京大教授の西洋史学者の増刷分が参考になるにしても、小林秀雄の初版三千部は少ない。あんまりだ。
他社に目を移すと、太宰治の短編集『八十八夜』三万五千部(南北書園、昭和21・3)というのは例外としても、柳田國男『先祖の話』一万部(筑摩書房、昭和21・4)、文学関係では川田順『細川幽斎』五千部(甲文社、昭和21・4。翌月に再版二千部)、高安国世『新しき力としての文学』五千部(秋田屋、昭和21・4)とどれも『無常といふ事』よりも多い。『無常といふ事』と同じような薄い本としては、パウムガルテン著、金子武蔵訳『戦争の道徳的反省』五千部(筑摩書房、昭和21・3)がある。文学史の評価を考えれば、『無常といふ事』の単行本がいかに地味なスタートだったか。無名の新人のような扱いで世に送り出された。