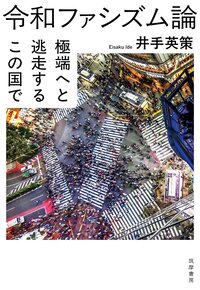単行本『無常といふ事』がやっと出る(一)
謹慎の身分で当局を全面批判
ここで河上が言及しているのは、正月元旦の各新聞を大々的に飾った真珠湾攻撃の上空からの写真についての小林の感想である。問題の原稿「戦争と平和」は、小林の今ここで行なわれている戦争へのさまざまな思いが交錯している。その中には、戦争報道批判をしている部分がある。
「戦場に於ける達人達の群れを見よ。戦争文学と戦争の文学的報道の氾濫が、国民の勇気を鼓舞しているなどと思ったら飛んだ間違いであろう。そういうものは、人々の戦争に関する空想を挑発し、戦争の異常性に就いて無要な饒舌を弄する足しになっているだけである。戦争ファンという怪物、正銘のパラドックスは、そちらにある、と言った方がいゝ」
物議を醸したのはこの部分ではと私には思える(現行のテキストは大幅に書き換えてある)。巷に溢れかえる、官主導の空疎な戦争報道一般を切り捨てているからだ。謹慎中の身であるべきなのに、当局への全面的な批判をする。これではすぐに目をつけられたろう。河上徹太郎は「文學界」翌月号の「文芸時評」の中で、特にこの小林の文章に触れ、弁護を試みている。時評家としてというより、「文學界」の責任編輯者としての弁である。
「小林秀雄が本誌前号で述べているハワイ爆撃の写真を見ての感想[「戦争と平和」]は非常に誤解され易いが、然し心ある者は必ず同感する真剣な実感である。彼はあの写真から生ずる誇張された感動詞を捨てて、率直に機械的に、あの図式を見ろというのだ。恐らくあすこを飛んでいた荒鷲[搭乗員]の眼には、あの通り正確な見取図としてしか映らなかった筈だというのだ。正にその通りである。平出[英夫]大佐の談によれば、練習の方が実戦より遥かに困難だという。私はその言葉を懸値なしに受取る。では何故人々は実戦よりも訓練の写真や記事を見て感動の言葉を湧き立たせようとしないのか? すべて戦場の「歴史的瞬間」の報道に関する諸工作に、文化的な意味や理窟を見出そうとした揚句、国民を誇張された感傷的空想に溺れさせる誤謬が、現在余りにも我々の身辺に多過ぎるのである。
誤解しないでほしいが、私は現地にあって我々の仲間[戦地に徴用された文士達]が、すべて徒に汗や血を流しているといっているのではない。そこで我々は、「潰し」として、或は縁の下の力持ちとして、色々御役に立っているであろう。又そこで接した稀有の現実や体験の数々は、必ず我々の魂や視神経にみそぎの作用をかけ、それが後年我々の人間や筆力の糧として重要な役目を尽すことを信じている。只私は、自他共に余りに報道文に期待をかけ過ぎ、筆者がこゝに文筆家としての矜りを保とうとし、読者が或る種のセンセイショナリズムを[に]満足しようとすることの危険を警告したいのである」