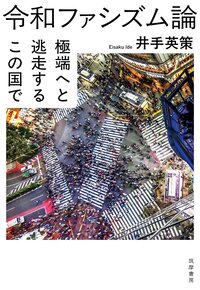単行本『無常といふ事』がやっと出る(一)
【連載第十一回】
平山周吉(ひらやま・しゅうきち)
戦時下の執筆制限、寄稿は文芸誌のみに
第一段階については、小林の秘書役だった郡司勝義が『歴史の探究――わが小林秀雄ノート・第三』で、おそらく本人の直話に基いて書いている。昭和十六年三月四日に朝日新聞のコラム「曳光弾」欄に載った短文「歩け、歩け」が問題にされる。高村光太郎作詞、飯田信夫(女優・夏川静江の夫)作曲の国民歌謡にモノ申した。「こんなヘンテコな歌が、生れでてくる現代日本のヘンテコな文明の得体の知れぬ病気状態が僕にはもうかなわぬ」。「国民歌謡」とは内閣情報部と日本放送協会がラジオを使ってのプロパガンダで、かかる国策に小林は批評の矢を放った。
「国民歌謡は戦時下の官製品と言ってよかったから、背後には当然国民精神総動員運動が控えていた。その連中をいたく刺戟したのである。しかも、この運動は昭和十五年十月に大政翼賛会へと発展解消されて、人脈はすべて温存され、組織は拡大された。そのため、権勢は拡大され、一段と活字文化へ嘴を入れ圧迫してきたのである。まさに、権力を笠に着ていた。小林は、それに睨まれたのである」(郡司『歴史の探究』)
取締当局は八月半ばに口頭で通達を発した。「総合雑誌とか新聞とか目立つ場所への寄稿は遠慮されたい。文藝誌のみならば、読者の数はずっと少いし限られているから、そちらの方はよろしい」という妥協案だった。「一中、一高で同級だった連中が多数中央官庁で実務上の現場にいて、お先走りの輩の言などに耳を傾けず、われらが代表選手は良識の主であると信じ巧みに庇う挙に出ていたから、危ない目には合わずに済んだ」という。この後、小林の発表舞台は「文學界」と「文藝」の二誌にほぼ限られた。「文學界」の責任編輯者だった河上徹太郎は、小林の原稿料を一枚いくらでなく一篇いくらとして優遇し、小林を助けた。