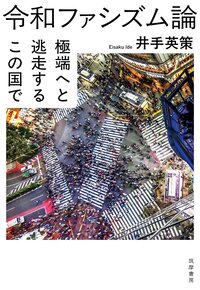単行本『無常といふ事』がやっと出る(一)
【連載第十一回】
平山周吉(ひらやま・しゅうきち)
発売半年にして「名著」入り
創元社はこの年の九月に、早々と「百花文庫」という廉価版のシリーズの中に『無常といふ事』を入れた。定価は七円、紙はインディアン・ペーパーを使用している。百科文庫には既に山本有三『不惜身命』、谷崎潤一郎『三人法師』、高浜虚子『子規句解』などが入っており、『無常といふ事』は八冊目だった。発売後半年にして、いわば「名著」認定されたのだ。入手もしやすくなったであろう。
書評や当時の読者の受け取りかたも後回しにして、『無常といふ事』という本の前史を探ってみたい。昭和三十年(一九五五)から刊行された最初の新潮社版『小林秀雄全集』の月報に、吉田健一が書いた「図書目録」というエッセイの中に証言がある。
「「無常といふ事」は、戦時中に情報局がどうしても出版を許さなくて、戦後になって創元社から出た」(新潮文庫『この人を見よ――小林秀雄全集月報集成』に所収)
たったこれだけだが、「近代文学」での小林の発言「僕の書いたものは戦争中禁止された。処が今だって出せるかどうかあやしいものだ」とも符合しそうだ。戦時下の小林の執筆制限、執筆への抑圧については、二段階で考えるのがどうもよさそうだ。第一段階は昭和十六年中盤の発表舞台の制限、第二段階が昭和十七年初めからの圧力、となる。